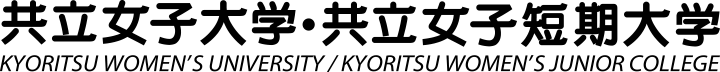文芸学部OGネットワーク
1.ようこそ 文芸OGネットワークへ
文芸OGネットワークは、文芸学部創設50周年を機に、卒業生のネットワークを作りたいという声が高まり、2003(平成15)年7月26日の50周年記念式典に於いて設立が発表されました。文芸学部卒業生、大学院文芸学研究科修了生ならだれでも入会できます。 活動としては、総会およびサロン講座の開催、共立祭参加、劇芸術専修研究室所蔵の演劇資料整理、会報『文芸OGネットワーク通信』の発行、『文藝学部報』の会員への送付などを行っています。 文芸OGネットワークに関心のある方は、下記連絡先にお問い合わせください。

連絡先
共立女子大学文芸学部芸術領域劇芸術専修研究室内 文芸OGネットワーク
〒101-8437
東京都千代田区一ツ橋2-2-1 共立女子大学文芸学部芸術領域研究室1421号室
Tel. 03-3237-2574
og-net@kyoritsu-wu.ac.jp

2.活動紹介
文芸OGネットワーク総会
文芸OGネットワーク総会は、午前中に総会が行われ、前年度の活動報告・今年度の活動予定・予算等が報告・審議されます。午後は、文芸サロン講座が行われるという形で開催しています。

総会・文芸サロン講座
2024(令和6)年度文芸OGネットワーク総会・文芸サロン講座開催のお知らせ
2024(令和6)年度の文芸OGネットワーク総会・文芸サロン講座を次の通りに開催します。コロナ禍による中止以来4年ぶりの開催になります。午前中に総会(2023年度活動報告、会計報告、本年度の活動予定・予算案等の報告と審議)を行い、午後は文芸サロン講座が行われます。是非、ご参集くださいますようご案内申し上げます。
| 日時 | 2024(令和6)年6月8日(土) |
|---|---|
| 場所 | 神田一ツ橋キャンパス 本館204号室 |
| 総会 | 11:00~12:00 |
| 昼食・歓談 | 12:00~13:00 |
| 文芸サロン講座 | 13:00~15:00 |
| 講師:福嶋伸洋氏(文芸学部教授) 演題:「音楽と文学~ワークショップを通して~」(仮題) *文芸サロン講座には会員以外の方も参加できます。前もって上記連絡先までお申し込みください。 会員には、葉書にてご案内していますが、出欠のお返事は5月17日(金)までに必着でお願いします。 |
文芸サロン講座開催
文学・芸術の領域はもちろんのこと、様々な分野から講師をお招きしてお話しを伺います。総会同様、2020~2023年度は開催を見合わせました。
第14回サロン講座
2017(平成29)年6月10日
講師:佐藤和代氏(古代丹波歴史研究会会員)
テーマ 「古代史を学ぶための基礎知識」
日本の古代史、と言えば多くの人の頭にすぐ浮かぶのは、おそらく邪馬台国と卑弥呼の二つであろう。しかし、『魏志倭人伝』に記載されている「邪馬台国」論争のかげにおかれて、あまり触れられることのない日本側の正史『日本書記』に記された同時代の畿内、纒向で起こったことを振り返ることも重要なのではないか、と古代史研究家の佐藤和代氏は力説される。
佐藤氏が光をあてた人物は第10代天皇である崇神天皇である。崇神天皇の初期、纒向(古墳の見つかったところ)においては出雲、吉備、鳥取、丹波、北陸、東海等々の豪族が集まって共立政治を行い、その中心に孝靈天皇の皇女・倭迹迹日百襲媛(ヤマトトトヒモモソヒメ)を鬼道・道教の巫女として据えた。卑弥呼を彷彿させるが、邪馬台国とは違う、とされている。
政変を起こしたのは崇神天皇で、武埴安彦(タケハニヤスヒコ)、百襲媛(モモソヒメ)を退け、大和朝廷の御筆国天皇(ハツクニシラススメラミコト)となる。これ以前、疫病が国中に蔓延してどうにもならなくなった時、崇神天皇は自身の宮床(ミヤドコ)の三神(オオモノヌシノミコト、ヤマトオオクニタマノミコト、アマテラスオオミカミ)を宮殿の外に出し、それぞれの直系の子孫(男系男子の血筋)に祀らせることで沈静化を計っている.次の垂仁天皇の時、天照大神を伊勢に祀ることになり国の形が、共立体制・道教から大和朝廷・神道へと移行した。
我が国の精神風土は太陽を拝む自然神崇拝から道教→神道→神道・仏教へと変遷してきている。本来の意味は違っているが、道教に関する言葉は現在でも我々の身辺に溢れている。たとえば、道を究める、道徳、神道,武道、風水、鬼、祟り神、陰陽(師)などなど。古代は我々が思うほど遠い存在ではないのかもしれない、と佐藤氏は語られる。
佐藤氏は共立女子大学日本文学コース出身(1966年卒)でいらっしゃるが、万葉集の研究をすすめているうちに歴史に興味を持ち、気がついたら古代史研究にどっぷりはまっており、ついに古代丹波歴史研究会を立ち上げてしまった、という経歴の持ち主である。その熱情は事前に用意された膨大な資料によく示されている。1時間半の講演ではとても伝えきれなかった事柄については、機会を改めてぜひ伺いたい、との感想が多く寄せられた。

第14回サロン講座
第15回サロン講座
2018(平成30)年10月20日
講師:武藤剛史氏(共立女子大学文芸学部教授)
テーマ: 「モーツァルト最晩年(1791)の小曲を聞く」
文芸学部教授の武藤剛史先生を講師にお迎えし、「モーツァルト最晩年(1791)の小曲を聞く」と題してお話しいただいた。先生がモーツァルトの音楽に造詣が深いことは関係者の間では知られている。今回の講演のきっかけとなったのは、『研究ファイル41』(2012)に書かれた「私家版・モーツァルトのピアノ協奏曲ガイド」である。これを読んだ会員からモーツァルトに関するお話を伺いたいという要望があり、文芸サロン講座のテーマとなった。プルースト研究で知られる武藤先生だが、講師を快諾してくださった。
講演は35歳で夭逝した音楽家がその最晩年(1791年)に作曲したいくつかの小曲を聞きながら解説を伺うという形で進められた。以下講演要旨によると、モーツァルトは、その前年に当たる1790年には5曲しか作曲していない。聴衆に見放されたこと、経済状態の悪化、後ろ盾だった皇帝ヨーゼフ二世の死去などの理由が考えられる。ところが1791年には30曲近くを作曲している。インスピレーションが枯渇した魂の死ともいえる状態から、自分の魂の真の根底を意識するに至って再生を果たし、創造力は復活した。しかし、この年の終わりには自らの死を迎えている。
今日でも私達がモーツァルトの音楽を耳にする機会は多い。その音楽について先生は「モーツァルトの音楽は自己表現ではない。むしろ彼は、自己を無にして、自己の内的宇宙から響いてくる音楽に聴き入り、その音楽になりきろうとする」(『研究ファイル 41』)と述べられている。時代を超えて聞く人を魅了してきた理由はそこにあるのではないか。
一般的なメディアが伝えるモーツァルト像には、映画『アマデウス』のように、世俗的な人物像や奇矯なふるまいが強調されたものが多いと感じる。世間では俗なる天才がこの上なく純粋な音楽(先生はよく「純粋」という言葉を使われている)を生み出したといった意外性が好まれるせいなのだろうか。
15回を数える文芸サロン講座だが、音楽をテーマとした講演は初めてであった。先生のモーツァルト愛に導かれ幸せな時間を過ごすことができた。
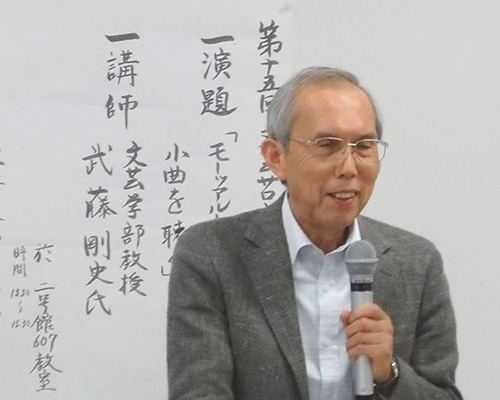
第15回サロン講座
第16回サロン講座
2019(令和1)年5月25日
講師:入江和生氏(共立女子大学名誉教授・前学長)
テーマ: 「女と男はこんなにも違う~英米女性作家に学ぶ」
何とも刺激的なタイトルである。入江先生はまず男性作家による女性の描かれ方を考察される。選ばれた作品は、ジェフリー・チョーサー「バースの女房の話」(『カンタベリー物語』)(1400),ウイリアム・シェイクスピア『ロミオとジュリエット』(1597)、ナサニエル・ホーソン『緋文字』(1850)、トマス・ハーディ『テス』(1891)。年代も環境も違うのだが、これらの作品で描かれる女性たちはどれも逞しく、時に男性をリードしかねない。代表はジュリエットであろうか。あの有名なせりふ「名前に何があるというの?」に示されるように、親同士の争いにこだわるロミオに対して、ジュリエットはひたすら愛の強さを訴えロミオをひっぱっていく。
女性作家の作品から選ばれたのは、シャーロット・ブロンテの『ジェーン・エア』(1894)ケイト・ショパン「一時間の物語」(『めざめ』)(1899)、ウイラ・キャザー『わが生涯の敵』(1926)、カーソン・マッカラーズ「悲しい酒場の歌」(1951)、ミュリエル・スパーク『あっち行け鳥』(1958)、アイリス・マードック『イタリア人の女』(1964)である。女性作家たちも、上にのべた男性作家たちのように、自立心の強い女性たちを描いている。たとえば、ジェイン・エアはもはや男性の庇護のもとに生きるのではなく、自分で運命を切り開く力強さをもっている。さらに言うならば、女性作家と男性作家の作品を比べてみると、時代が現代にちかづくにつれ、女性作家たちの描く主人公は、自分たちが欲するがままに奔放に生きていく女性が増えており、「社会通念としての『女らしさ』を拒絶しているようだ」と入江先生は述べられる。男性作家の描く女主人公たちの目標が結婚にあるならば、女性作家の描く主人公は「もはや「結婚」という制度にしばられてはいない」とも述べられる。そのことを端的に示す言葉は、ケイト・ショパンの『めざめ』の最後の一文「結婚はこの世で最も嘆かわしい光景の一つだ」であろう。
受講者の中には在学中入江先生のシェイクスピアの講義を受けた英文学コース出身者が多かったのだが、次回は是非イギリス女性作家の代表ともいうべき、ジェイン・オースティンとヴァージニア・ウルフを取りあげていただきたい、という希望が多く寄せられたところで、興味深い文学談義が終わったのである。

第16回サロン講座
共立祭参加
2020年、2021年はコロナ感染症の影響で外部からの参加はできませんでした。2022、2023年度は、新型コロナ感染症が未だ収まらないため参加を見合わせました。今年については未定ですが、参加が決まった場合は、このページでお知らせします。

共立祭
芸術領域劇芸術専修研究室資料整理
劇芸術専修研究室の所蔵する演劇関係資料の整理のお手伝いをしています。演劇資料整理は毎週火曜日、13:00~15:00、3号館大学院棟5階演劇資料室にて行っています。大学の休暇期間に合わせて休室します。関心のある方は、上記連絡先までお問い合わせください。
文芸OGネットワーク通信発行
年1回、『文芸OGネットワーク通信』を発行しています。現在の大学の情報を提供するとともに卒業生の情報交換の場になることを目指しています。合わせて『文藝学部報』もお送りしています。
アーカイブス
文芸サロン
第11回文芸サロン講座
- 小池淳一氏(国立歴史民俗博物館教授)「東日本大震災と民俗文化資源」
-
講師に国立歴史民俗博物館教授、小池淳一氏をお迎えし、「東日本大震災と民俗文化資源」という演題で行われました。東北の震災からこの3月11日で早や3年の月日が過ぎ、復興もままならぬ現状にもかかわらず、私達の記憶から遠のいていきつつあるのではないか。そうしたなかでの今回の講演は意義深いものがあったのではないでしょうか。
小池氏は、ご自身の専門分野である民俗学を通して、復興にもかかわってこられました。永年の研究対象である東北―特に気仙沼市小々汐(こごしお)地区、通称小々汐オオイ(大本家)の調査中に起きた今回の震災を通して、文化資源をどう再生させるか、またその意義について述べられました。民俗学とは、形あるものから、目に見えない部分までかかわりを持ち、精神の連続性をテコにしている学問であるという視点から、文化資源をどのようにとらえ、再生させるかが課題であったとのことでした。13,000点以上に及ぶ資料の救出、整理作業を通して新しい文化資源の活用の模索がはじまったとのことです。
最後にあの震災を忘れぬことが、震災からの復興を手助けする大切な姿勢であり、応援ですと結ばれました。
第11回文芸サロン講座
第12回文芸サロン講座
- 内田保廣先生(文芸学部教授)「江戸の面影~浅草からの江戸の遊び場~
-
講師は、文芸学部教授の内田保廣先生で、演題は「江戸の面影~浅草からの江戸の遊び場~」でした。しばし江戸時代にタイムスリップしたかのような2時間の講座でした。プロジェクターを駆使して、江戸時代の様々な興味深い事柄を終始軽妙な語り口で説明してくださいました。
まず、江戸の始まりとしての浅草ということで、金龍山浅草寺を紹介してくださいました。浅草寺の起源は、寺伝によれば推古天皇36年(628年)だそうです。そんなに古い時代から存在していたお寺だとは露知らず、21世紀の現在も、常に人が集まり、海外からの観光客をも魅了する、東京観光には欠かせない有名な浅草寺を日本人として改めて誇りに思いました。江戸時代のモードは遊女、芝居からということで、モードを生み出す場所としての役割も浅草にはあったようです。
今回のお話しを伺って、東京に住んでいながら、未だ行ったことのない浅草周辺の下町辺りと、何回も行ったことはありますが、あの有名な浅草寺に、もう一度行ってみたくなりました。江戸時代に思いを馳せながら・・・。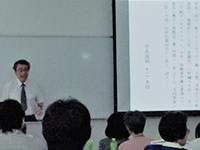
第12回文芸サロン講座
第13回サロン講座
- 山本聡美先生(文芸学部教授)「九相図からよみとく、女性の身体と信仰」
-
日本中世絵画史、特に「九相図」の研究をされている山本聡美先生(文芸学部教授)の講演で、演題は、「九相図からよみとく、女性の身体と信仰」でした。「九相図」とは、僧侶が肉体への執着を断ち切るために「九相観」と呼ばれる仏教の修行に用いられた図像だそうです。その修行は、本来、実物の死体の不浄の様子をよく観察し、腐り、骨になるまでを見届け、そのイメージを静かな場所で精神統一しながらもう一度思い浮かべて、心が乱れてきたら落ち着かせ、それを繰り返して人間の肉体の儚さを思うというものだそうです。「九相図」に描かれる絵は、女性が段々朽ちていく図が多く、鎌倉時代から江戸時代にかけてよく製作されていたものです。中世の日本の説話文学には、九相観に関連する話が多いそうです。仏教では女性の肉体そのものが不浄と考えられていましたが、女性が不浄を自覚し、男性の発心を促したという善行によって、女性もまた仏教へ関与する道が開かれたといった読み替えが行われているとおっしゃっていました。
日本で成立した九相観説話の中には、美貌の女性や高貴な女性の死屍がさらされるというシチュエーションが多く、その背景には、女人教化の目的で九相観説話が大いに喧伝された側面が伺えるということです。鎌倉時代から江戸時代にかけて、「九相詩絵巻」が数多く作られました。
丁寧な資料を用意して下さって、予定の時間を少し過ぎるくらい内容の濃いお話しをうかがうことができました。
第13回サロン講座