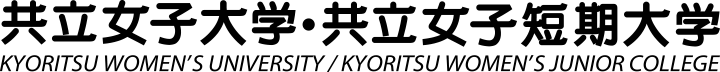学長メッセージ
「リーダーシップの共立®」
本学では、第三期中期計画のビジョン2032を「誰もが『Major in Anything. Minor in Leadership.®』を実感できる大学・短期大学を目指す」としています。
本学の学生は所属する学部・学科・科の「専門分野」を主専攻として学ぶと共に、すべての教育活動を通して、全員がリーダーシップを学びます。「Major in Anything. Minor in Leadership.®」(主専攻は様々な専門分野、副専攻はリーダーシップ)とは、この学部・科の専門的な知識・技能の活用とリーダーシップの発揮の2つの関係性を表現したものです。
近年、女子大学の志願者数は減少傾向にあり、一部では共学化が進むなど、女子大学は厳しい状況に直面しています。しかし、日本のジェンダーギャップ指数が示している通り、女子大学にはまだまだ果たすべき社会的役割があり、女子大学だからこそできる教育があると考えています。そのひとつがリーダーシップ教育です。
本学が開発・育成するリーダーシップは「みずからを恃(たの)み『自立』し、『友愛』により他者と協働して目標達成を目指す力」であり、これを「共立リーダーシップ®」と名付けました。ここでいうリーダーシップはトッブダウン型ではなく、相互支援型のものです。定義の前半は、建学の精神である「女性の自立と自活」によります。後半は、「誠実・勤勉・友愛」という本学の校訓に根差した言葉です。
本学には「リーダーシップ」に対応した授業科目は全学でおよそ300科目開設されていますが、2025年度からは全学共通科目に「課題解決のためのリーダーシップ入門」(必修科目)を設置し、より一層リーダーシップ教育に力を入れていきます。
2024年11月に「リーダーシップの共立®」、「共立リーダーシップ®」が商標登録されたことも、本学のリーダーシップ教育に対する姿勢を示すものです。
学生の皆さんが、学生生活の様々な場面で「共立リーダーシップ®」を身につけ、成長されることを期待しています。

共立女子大学・共立女子短期大学
学長 佐藤 雄一