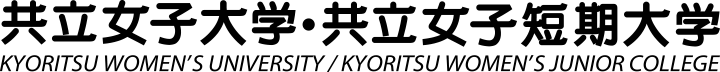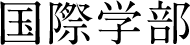Faculty of International Studies
еӣҪйҡӣеӯҰйғЁгғӢгғҘгғјгӮ№и©ізҙ°
жӣҙж–°ж—Ҙпјҡ2025е№ҙ07жңҲ08ж—Ҙ
еӯҰз”ҹгҒ®жҙ»еӢ•
гҖҗеӣҪйҡӣеӯҰйғЁгҖ‘еӯҰз”ҹеәғе ұ委員гҒ«гӮҲгӮӢж–°д»»ж•ҷе“ЎпјҲдёӯжқ‘й•·еҸІе…Ҳз”ҹпјүгҒёгҒ®гӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғј
гҖҖ2025е№ҙеәҰжҳҘгҖҒеӣҪйҡӣеӯҰйғЁгҒ«ж–°д»»ж•ҷе“ЎгҒЁгҒ—гҒҰзқҖд»»гҒ—гҒҹеӣҪйҡӣж”ҝжІ»еӯҰгҒҢе°Ӯй–ҖгҒ®дёӯжқ‘й•·еҸІе…Ҳз”ҹгҒ«гҖҒеӯҰз”ҹеәғе ұ委員гҒ®й Ҳз”°гҖҖжҷҙиҸңгҒ•гӮ“пјҲеӣҪйҡӣеӯҰйғЁ1е№ҙпјүгҒҢгӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғјгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®жЁЎж§ҳгӮ’гҒҠеұҠгҒ‘гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
в—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Ү
Q.е…Ҳз”ҹгҒҢе°Ӯж”»гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢеӣҪйҡӣж”ҝжІ»еӯҰгҒЁгҒҜгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӯҰе•ҸгҒ§гҒҷгҒӢпјҹ
гҖҖгҒқгӮӮгҒқгӮӮж”ҝжІ»еӯҰгҒ®еҪ№еүІгҒ®дёҖгҒӨгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢгҖҢеҲ©е®ігӮ„дҫЎеҖӨиҰігҒ®йҒ•гҒҶдәәгҖ…гҒҢдҪ•гҒЁгҒӢдёҖз·’гҒ«з”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гҒ‘гӮӢж–№жі•гҖҚгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеӣҪйҡӣж”ҝжІ»еӯҰгҒҜгҒқгӮҢгҒ®еӣҪйҡӣзүҲгҖҒгҒӨгҒҫгӮҠгҖҢеҲ©е®ігӮ„дҫЎеҖӨиҰігҒ®йҒ•гҒҶеӣҪгҖ…гҒҢдҪ•гҒЁгҒӢдёҖз·’гҒ«з”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гҒ‘гӮӢж–№жі•гҖҚгӮ’иҖғгҒҲгӮӢеӯҰе•ҸгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеӣҪйҡӣж”ҝжІ»еӯҰгҒҜ第дёҖж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰеҫҢгҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгҒҹеӯҰе•ҸгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжҲҰдәүгҒҢиө·гҒ“гӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҒ©гҒҶгҒҷгӮҢгҒ°гӮҲгҒ„гҒ®гҒӢгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒеӣҪйҡӣж”ҝжІ»еӯҰгҒ§гҒҜгҖҒгҒҫгҒҡжҲҰдәүгҒҢиө·гҒ“гӮӢеҺҹеӣ гӮ’зӘҒгҒҚжӯўгӮҒгҖҒгҒқгҒ®еҺҹеӣ гӮ’еҸ–гӮҠйҷӨгҒҸгҒ“гҒЁгҒ§е№іе’ҢгҒ«иҝ‘гҒҘгҒ“гҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ—гғӯгғјгғҒгӮ’гҒЁгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҠеҢ»иҖ…гҒ•гӮ“гҒҢжӮЈиҖ…гҒ•гӮ“гҒ®з—…ж°—гҒ®еҺҹеӣ гҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҖҒи–¬гӮ’еҮәгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒжүӢиЎ“гӮ’гҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгӮӨгғЎгғјгӮёгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒеӣҪйҡӣж”ҝжІ»еӯҰгҒҜиІҝжҳ“гӮ„й–ӢзҷәгҖҒз’°еўғгҖҒж–ҮеҢ–гҒӘгҒ©ж§ҳгҖ…гҒӘдәӢжҹ„гӮ’жүұгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжҲҰдәүгҒЁе№іе’ҢгӮ’гӮҒгҒҗгӮӢе•ҸйЎҢгҒҜзҸҫеңЁгҒ§гӮӮйҮҚиҰҒгҒӘз ”з©¶еҜҫиұЎгҒ§гҒҷгҖӮ
.png)
пјұ.е…Ҳз”ҹгҒҢиҖғгҒҲгӮӢеӣҪйҡӣж”ҝжІ»еӯҰгҒ®йҶҚйҶҗе‘ігҒҜдҪ•гҒ§гҒҷгҒӢпјҹ
гҖҖеғ•гҒҢиҖғгҒҲгӮӢеӣҪйҡӣж”ҝжІ»еӯҰгҒ®йҶҚйҶҗе‘ігҒҜгҖҒ“гғҮгӮЈгғ¬гғігғһ”гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеғ•гҒ®жҢҮе°Һж•ҷе“ЎгҒ гҒЈгҒҹзҹіз”°ж·іе…Ҳз”ҹгҒҢгӮҲгҒҸд»°гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮ“гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеӣҪйҡӣж”ҝжІ»гҒ«гҒҜдёЎз«ӢгҒ—гҒӘгҒ„гҒ‘гҒ©гҖҒгҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҒ©гҒЎгӮүгҒӢгӮ’гҒӮгҒҚгӮүгӮҒгӮӢгҒ®гӮӮе«ҢгҒ гҒЁгҒ„гҒҶзҠ¶жіҒгҒҢгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒӮгӮӢгӮ“гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°ж—ҘеёёгҒ§гӮӮгҖҒеӨңдёӯгҒ«гӮўгӮӨгӮ№йЈҹгҒ№гҒҹгҒ„гҒ‘гҒ©гҖҒеӨӘгӮӢгҒ®гҒҜе«ҢгҒ гҒӘ……гҒЈгҒҰгҒ“гҒЁгҒӮгӮӢгҒҳгӮғгҒӘгҒ„гҒ§гҒҷгҒӢпјҲ笑пјүгҖӮеӣҪйҡӣж”ҝжІ»гҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒҢгӮӮгҒЈгҒЁгӮ·гғ“гӮўгҒ§гҖҒдәәгҒҢз”ҹгҒҚгӮӢгҒӢжӯ»гҒ¬гҒӢгҖҒеӣҪ家гҒ®йҒӢе‘ҪгҒҢгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгӮ“гҒ§гҒҷгҖӮ
гғҮгӮЈгғ¬гғігғһгҒЈгҒҰгҖҒгҒ©гҒЈгҒЎгҒӢгҒ гҒ‘гҒҢ“жӯЈгҒ—гҒ„”гҒЈгҒҰгҒ„гҒҶи©ұгҒҳгӮғгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮеӨҡгҒҸгҒҰгҖӮгҒ©гҒЈгҒЎгӮӮдёҖзҗҶгҒӮгӮӢгҒ‘гҒ©гҖҒдёҖж–№гӮ’з«ӢгҒҰгӮҢгҒ°гҖҒгӮӮгҒҶдёҖж–№гҒҢз«ӢгҒҹгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгӮҢгҒҢзҸҫе®ҹгҒӘгӮ“гҒ§гҒҷгӮҲгҖӮгҒ гҒӢгӮүгҖҒжң¬еҪ“гҒ«гҒ„гҒ„гҒ“гҒЁгҒЈгҒҰгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒЁгҒ—гҒҹгӮ№гғ”гғјгғүгҒ§гҒ—гҒӢйҖІгҒҫгҒӘгҒ„гҒ—гҖҒеғ•гҒҜгӮҖгҒ—гӮҚгҒқгҒҶгҒӮгӮӢгҒ№гҒҚгҒ гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒиӢҘгҒ„й ғгҒҜгҖҒгҖҢжҳҺж—ҘгҒ«гҒҜдё–з•ҢгҒҢеҠҮзҡ„гҒ«гӮҲгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҖҚгҒЈгҒҰжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮ“гҒ§гҒҷгҒ‘гҒ©гҖҒд»ҠгҒҜгӮӮгҒҶгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁгҖҒгҒҳгҒЈгҒҸгӮҠгҒ§гҒ„гҒ„гӮ“гҒҳгӮғгҒӘгҒ„гҒӢгҒӘгҒЈгҒҰгҖӮ
гҖҢгӮҲгҒҚгҒ“гҒЁгҒҜгӮ«гӮҝгғ„гғ гғӘгҒ®йҖҹеәҰгҒ§йҖІгӮҖгҖҚгҒЈгҒҰиЁҖи‘үгҒҢгҒҫгҒ•гҒ«гҒқгҒҶгҒ гҒӘгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгӮӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒҹгӮүгҖҒиҮӘеҲҶгҒҢз”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒҶгҒЎгҒ«зӯ”гҒҲгҒҜеҮәгҒӘгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒ‘гӮҢгҒ©гҖҒгҒ гҒӢгӮүгҒ“гҒқиҖғгҒҲз¶ҡгҒ‘гӮӢж„Ҹе‘ігҒҢгҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
Q.еӣҪйҡӣж”ҝжІ»еӯҰгӮ’е°Ӯж”»гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҹгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒҜпјҹ
гҖҖгҒқгӮҢгҒҜгҖҒзҗҶз”ұгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸеҲҶгҒ‘гҒҰ3гҒӨгҒӮгҒЈгҒҰгҖӮ1гҒӨзӣ®гҒ®зҗҶз”ұгҒҜгҖҒеғ•гҒ®дёӯеӯҰгғ»й«ҳж ЎжҷӮд»ЈгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮдёӯй«ҳдёҖиІ«ж ЎгҒ«йҖҡгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒй«ҳж ЎеҸ—йЁ“гҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒдёӯеӯҰгҒ®й ғгҒӢгӮүгҒ‘гҒЈгҒ“гҒҶиҮӘз”ұгҒ«еҘҪгҒҚгҒӘгҒ“гҒЁгӮ’гӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖӮгҒқгҒ®й ғгҒЈгҒҰгҖҒдё–з•ҢгҒ§гҒҜгҒ„гӮҚгӮ“гҒӘеҮәжқҘдәӢгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮ“гҒ§гҒҷгӮҲгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°2001е№ҙгҒ®гӮўгғЎгғӘгӮ«еҗҢжҷӮеӨҡзҷәгғҶгғӯгҒЁгҒӢгҖҒ2003е№ҙгҒ®гӮӨгғ©гӮҜжҲҰдәүгҒЁгҒӢгҒӯгҖӮзҡҶгҒ•гӮ“гҒ®дё–д»ЈгҒ гҒЁж•ҷ科жӣёгҒ§зҝ’гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеҗҢжҷӮд»Јзҡ„гҒ«иө·гҒҚгҒҰгҒ„гҒҹгӮ“гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒҶгҒ„гҒҶжҷӮд»ЈгҒ«гҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁиғҢдјёгҒігҒ—гҒҰжң¬гӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гҒ„гҒҰгҖҒж”ҝжІ»гҒЁгҒӢеӣҪйҡӣй–ўдҝӮгҒ®жң¬гӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гҖҒгҖҢгҒӮгҒӮгҖҒгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶеҲҶйҮҺгҒҢгҒӮгӮӢгӮ“гҒ гҒӘгҖҒйқўзҷҪгҒқгҒҶгҖҚгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒ®гҒҢжңҖеҲқгҒ®гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҖҢеӨ§еӯҰгҒ§гҒҜж”ҝжІ»еӯҰгӮ’еӢүеј·гҒ—гӮҲгҒҶгҖҚгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶеӯҰйғЁгҒ«е…ҘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖ2гҒӨзӣ®гҒ®зҗҶз”ұгҒҜеӨ§еӯҰжҷӮд»ЈгҒ«жЁЎж“¬еӣҪйҖЈгӮ’иЎҢгҒҶгӮөгғјгӮҜгғ«гҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒӘгӮ“гҒ§гҒҷгҖӮ模擬еӣҪйҖЈгҒЈгҒҰгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒгҒІгҒЁгӮҠгҒІгҒЁгӮҠгҒҢеҗ„еӣҪгҒ®ж”ҝеәңд»ЈиЎЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«д»ЈиЎЁгҒЁгҒӢдёӯеӣҪд»ЈиЎЁгҒЁгҒӢгҒ«гҒӘгӮҠгҒҚгҒЈгҒҰдәӨжёүгҒҷгӮӢгҖҒгғӯгғјгғ«гғ—гғ¬гӮӨеҪўејҸгҒ®жҙ»еӢ•гҒӘгӮ“гҒ§гҒҷгҒ‘гҒ©гҖҒгҒқгӮҢгҒҢгҒҷгҒ”гҒҸйқўзҷҪгҒҸгҒҰгҖҒжҺҲжҘӯд»ҘеӨ–гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гӮӮгҖҒгҒҡгҒЈгҒЁеӣҪйҡӣж”ҝжІ»гҒ«и§ҰгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ гҒӢгӮүеӯҰйғЁжҷӮд»ЈгҒҜгҖҒиӘІеӨ–жҙ»еӢ•гӮӮеҗ«гӮҒгҒҰгҖҒеӣҪйҡӣж”ҝжІ»гӮ’гҒӢгҒӘгӮҠгҒҢгҒЈгҒӨгӮҠгӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰ3гҒӨзӣ®гҒ®зҗҶз”ұгҒҜгӮјгғҹгҒ§гҖҒеӯҰйғЁгҒ§гҒҜж”ҝжІ»е“ІеӯҰгҒ®гӮјгғҹгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒж”ҝжІ»жҖқжғігҒЁгҒӢе“ІеӯҰзҡ„гҒӘгҒ“гҒЁгӮ’еӢүеј·гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮ“гҒ§гҒҷгҒ‘гӮҢгҒ©гӮӮгҖҒгҒқгҒ®е№ҙгҒ«ијӘиӘӯгҒ—гҒҹгҒ®гҒҢеӣҪйҡӣж”ҝжІ»жҖқжғігҒ®жң¬гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮеғ•гҒҜгҖҒгӮҸгӮҠгҒЁжҠҪиұЎзҡ„гҒ«зү©дәӢгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒ®гҒҢеҘҪгҒҚгҒ§гҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҒҜж”ҝжІ»е“ІеӯҰгӮӮгҒҷгҒ”гҒҸжҘҪгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгӮ“гҒ§гҒҷгӮҲгҖӮ
.jpg)
_____гҒқгҒ“гҒӢгӮүгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰеӣҪйҡӣж”ҝжІ»гҒёпјҹ
гҖҖгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁеӣҪйҡӣж”ҝжІ»гҒ«й–ўеҝғгҒҢеј·гҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒЁгҖҒ模擬еӣҪйҖЈгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҒҡгҒЈгҒЁзҸҫе®ҹгҒ®еӣҪйҡӣе•ҸйЎҢгҒ«еҗ‘гҒҚеҗҲгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒж°—гҒҘгҒ‘гҒ°й–ўеҝғгҒҢгҒқгҒЈгҒЎгҒ«гӮ·гғ•гғҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮ“гҒ§гҒҷгӮҲгҒӯгҖӮгҒ гҒӢгӮүеӨ§еӯҰйҷўгҒ«йҖІгӮҖгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢгҒӮгҒӮгҖҒгӮ„гҒЈгҒұгӮҠеӣҪйҡӣж”ҝжІ»еӯҰгӮ’гӮӮгҒЈгҒЁж·ұгҒҸгӮ„гӮҠгҒҹгҒ„гҒӘгҖҚгҒЈгҒҰжҖқгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
Q.еӣҪйҡӣж”ҝжІ»гҒ®жҺҲжҘӯгҒЈгҒҰгҖҒгҒ©гӮ“гҒӘеӯҰз”ҹгҒ«гҒ“гҒқеҸ–гҒЈгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒӢпјҹ
гҖҖгҒҶгғјгӮ“гҖҒжӯЈзӣҙиЁҖгҒҶгҒЁгҒӯгҖҒеӣҪйҡӣеӯҰйғЁгҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒ«гҒҜе…Ёе“ЎгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒӘгҒӮпјҲ笑пјүгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒиҮӘеҲҶгҒҢдҪ•гӮ’е°Ӯй–ҖгҒ«гҒҷгӮӢгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢйҒ•гҒҶгҒЁжҖқгҒҶгӮ“гҒ§гҒҷгҒ‘гҒ©гҖҒгҒҫгҒҡгҒҜ1е№ҙз”ҹгҒ®гҒҶгҒЎгҒҜгҖҢеӣҪйҡӣй–ўдҝӮе…Ҙй–ҖгҖҚгҒЁгҒӢгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶеҹәжң¬зҡ„гҒӘжҺҲжҘӯгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒҝгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮиҲҲе‘ігӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹдәәгҒҜгҖҒ2е№ҙз”ҹд»ҘйҷҚгҒ«зҷәеұ•зҡ„гҒӘ科зӣ®гӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒңгҒІз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮгҒҹгҒ гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒҶгҒЎгҒ®еӯҰйғЁгҒЈгҒҰд»–гҒ«гӮӮйқўзҷҪгҒ„жҺҲжҘӯгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҢгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒ«иЎҢгҒҚгҒҹгҒ„гҖҚгҒЁгҒӢгҖҒгҖҢгӮЁгғӘгӮўгҒ«иЎҢгҒҚгҒҹгҒ„пҪЈгҒЈгҒҰгҒ„гҒҶгҒ®гӮӮ全然гҒӮгӮҠгҒӘгӮ“гҒ§гҒҷгҖӮгҒ§гӮӮгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒқгҒЈгҒЎгҒ®йҒ“гҒ«йҖІгӮ“гҒ гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеӣҪйҡӣж”ҝжІ»гҒ®зҹҘиӯҳгҒЈгҒҰгҒҚгҒЈгҒЁгҒ©гҒ“гҒӢгҒ§еҪ№гҒ«з«ӢгҒӨгҒҜгҒҡгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгҒ гҒӢгӮүгҖҒгҖҢиӘ°гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒӢгҖҚгҒ§иЁҖгҒҶгҒӘгӮүгҖҒе…Ёе“ЎпјҒгҒ§гҒҷпјҲ笑пјүгҖӮ
.jpg)
QзҸҫеңЁгҒҜгҒ©гӮ“гҒӘз ”з©¶гӮ’гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮ“гҒ§гҒҷгҒӢпјҹ
гҖҖд»ҠгҒҜгҒ„гӮҚгӮ“гҒӘгғҶгғјгғһгҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгӮ“гҒ§гҒҷгҒ‘гҒ©гҖҒеғ•гҒҜзҗҶи«–зі»гҒ®з ”究иҖ…гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒең°еҹҹгҒЁгҒӢжҷӮд»ЈгӮ’йҷҗе®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгҖҒеӣҪйҡӣж”ҝжІ»е…ЁдҪ“гӮ’е®ҲеӮҷзҜ„еӣІгҒЁгҒ—гҒҰз ”з©¶гҒ—гҒҰгҒҫгҒҷгҒӯгҖӮ
гҖҖдёӯгҒ§гӮӮдёҖз•Әй•·гҒҸгӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгҖҒгҖҢжҲҰдәүгҒҜгҒӘгҒңзөӮгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгғҶгғјгғһгҒ§гҒҷгҖӮе°Ӯй–Җзҡ„гҒ«гҒҜгҖҢеҮәеҸЈжҲҰз•ҘгҖҚгҒЈгҒҰиЁҖгҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгӮ“гҒ§гҒҷгҒ‘гҒ©гҖӮ
жҲҰдәүгҒҢ“гҒ©гҒҶгӮ„гҒЈгҒҰе§ӢгҒҫгӮӢгҒӢ”гҒҳгӮғгҒӘгҒҸгҒҰгҖҒ“гҒ©гҒҶгӮ„гҒЈгҒҹгӮүзөӮгӮҸгӮӢгҒ®гҒӢ”гҒЁгҒ„гҒҶиҰ–зӮ№гҒ§з ”究гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеӣҪйҡӣж”ҝжІ»гҒ®з ”究гҒЈгҒҰгҖҒгҖҢжҲҰдәүгҒҜгҒӘгҒңе§ӢгҒҫгӮӢгҒ®гҒӢгҖҚгҒЈгҒҰгҒ„гҒҶз ”з©¶гҒҢдёҖз•ӘеӨҡгҒ„гӮ“гҒ§гҒҷгҖӮгҒҷгҒ”гҒҸеӨ§дәӢгҒӘгғҶгғјгғһгҒ гҒ—гҖҒжҳ”гҒӢгӮүгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ®дәәгҒҢз ”з©¶гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгҒ§гӮӮгҖҒжҲҰдәүгҒҢгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“е§ӢгҒҫгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒӮгҒЁгҖҒгҖҢгҒҳгӮғгҒӮгҒқгӮҢгӮ’гҒ©гҒҶгӮ„гҒЈгҒҰзөӮгӮҸгӮүгҒӣгӮӢгҒ®гҒӢгҖҚгҒЈгҒҰгҒ„гҒҶйғЁеҲҶгҒҜгҖҒж„ҸеӨ–гҒЁжүӢи–„гҒӘгӮ“гҒ§гҒҷгӮҲгҒӯгҖӮеғ•гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒе§ӢгҒҫгӮӢзҗҶз”ұгҒЁеҗҢгҒҳгҒҸгӮүгҒ„зөӮгӮҸгӮүгҒӣгӮӢж–№жі•гӮӮеӨ§дәӢгҒ гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ“гӮ’жҺҳгӮҠдёӢгҒ’гҒҰз ”з©¶гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
_____д»ҠеҫҢгҖҒеҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒҝгҒҹгҒ„з ”з©¶гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢпјҹ
гҖҖгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮеғ•гҒҜгҖҒгҖҢгҒӘгҒңжҲҰдәүгҒҢзөӮгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгҖҚгҒЈгҒҰгҒ„гҒҶгғҶгғјгғһгҒ§з ”究гҒ—гҒҰгҒҚгҒҰгҖҒзү№гҒ«гӮўгғЎгғӘгӮ«гҒҢгӮўгғ•гӮ¬гғӢгӮ№гӮҝгғігӮ„гӮӨгғ©гӮҜгҒ«й•·жңҹй–“й§җз•ҷгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«жіЁзӣ®гҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮўгғЎгғӘгӮ«гҒҜгӮўгғ•гӮ¬гғӢгӮ№гӮҝгғігҒ«гҒҜ2001е№ҙгҒӢгӮү2021е№ҙгҒҫгҒ§зҙ„20е№ҙй–“гҖҒгӮӨгғ©гӮҜгҒ«гӮӮ2003е№ҙгҒӢгӮү2011е№ҙгҒҫгҒ§гҖҒзҙ„9е№ҙиҝ‘гҒҸй§җз•ҷгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжң¬жқҘгҖҒгҒҠйҮ‘гӮӮдәәе‘ҪгӮӮгҒӢгҒӢгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜж—©гҒҸеј•гҒ„гҒҹж–№гҒҢеҗҲзҗҶзҡ„гҒӘгҒҜгҒҡгҖӮгҒ§гӮӮгҖҒгҒӘгҒңгҒӢгӮәгғ«гӮәгғ«гҒЁз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгҖҢеј•гҒҚгҒҹгҒҸгҒҰгӮӮеј•гҒ‘гҒӘгҒ„жҲҰдәүгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒҜз ”з©¶гҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜд»ҠгҒ®гғӯгӮ·гӮўгғ»гӮҰгӮҜгғ©гӮӨгғҠжҲҰдәүгҒЁгҒҜе°‘гҒ—з•°гҒӘгӮӢгӮҝгӮӨгғ—гҒ®жҲҰдәүгҒ§гҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«гҒҢзӣёжүӢгҒ«ең§еҖ’зҡ„гҒ«е„ӘдҪҚгҒӘз«Ӣе ҙгҒӢгӮүд»Ӣе…ҘгҒҷгӮӢжҲҰдәү——гҒ“гӮҢгӮ’“ж–°гҒ—гҒ„гӮҝгӮӨгғ—гҒ®жҲҰдәү”гҒЁгҒ—гҒҹгӮүгҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒЁгӮҰгӮҜгғ©гӮӨгғҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҖҢеҠӣгҒҢжӢ®жҠ—гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеӣҪеҗҢеЈ«гҒ®жӯЈйқўиЎқзӘҒгҖҚгҒҜгҖҒгӮҖгҒ—гӮҚ“еҸӨгҒ„гӮҝгӮӨгғ—гҒ®жҲҰдәү”гҒӘгӮ“гҒ§гҒҷгҖӮ
_____ж•ҷ科жӣёгҒ«еҮәгҒҰгҒҸгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘжҲҰдәүгҒЈгҒҰж„ҹгҒҳгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ
гҖҖгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮжӯЈзӣҙгҖҒеғ•гҒҜгӮӮгҒҶгҒқгҒҶгҒ„гҒҶжҲҰдәүгҒҜиө·гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒҹгӮ“гҒ§гҒҷгӮҲгҖӮгҒ§гӮӮе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒд»ҠгҒҫгҒ•гҒ«гҒқгҒҶгҒ—гҒҹжҲҰдәүгҒҢиө·гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүгҒ“гӮҢгҒӢгӮүгҒҜгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹ“еҸӨгҒ„гӮҝгӮӨгғ—гҒ®жҲҰдәү”гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠз ”з©¶гҒ—гҒҰгҒ„гҒӢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒӘгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
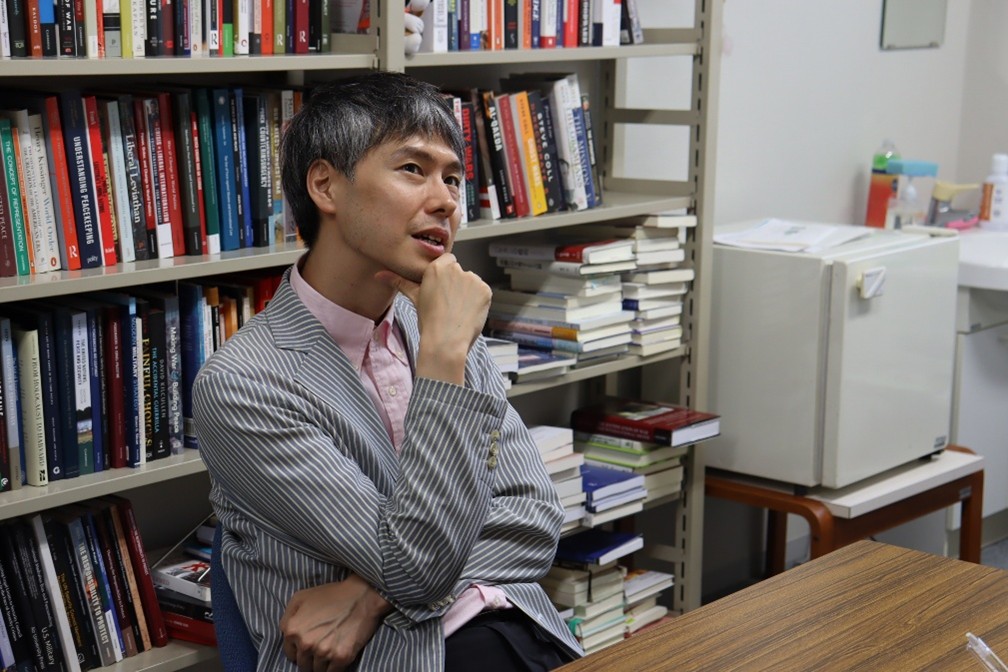
пјұ.гҒ“гӮҢгҒӢгӮүгҒ®жҷӮд»ЈгҒ«еӣҪйҡӣж”ҝжІ»еӯҰгӮ’еӯҰгҒ¶ж„Ҹзҫ©гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢпјҹ
гҖҖеҪ“然гҖҢгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒҜиЁҖгҒҲгҒӘгҒ„гҒ§гҒҷгӮҲгҒӯпјҲ笑пјүгҖӮгӮ„гҒЈгҒұгӮҠдјјгҒҹдәӢдҫӢгҒҢйҒҺеҺ»гҒ«гӮӮгҒӮгӮӢгҒЈгҒҰгҒ“гҒЁгҒӘгӮ“гҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»Ҡиө·гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“ж–°гҒ—гҒ„йғЁеҲҶгӮӮгҒӮгӮӢгӮ“гҒ гҒ‘гҒ©гҖҒеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒгғӯгӮ·гӮўгғ»гӮҰгӮҜгғ©гӮӨгғҠжҲҰдәүгҒҝгҒҹгҒ„гҒӘгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢ“еҸӨгҒ„гӮҝгӮӨгғ—гҒ®жҲҰдәү”гӮӮгҒҫгҒҹиө·гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгӮҲгҒӯгҖӮеӨ§еӣҪгҒҢйҡЈгҒ®еӣҪгҒ«и»ҚдәӢдҫөж”»гҒҷгӮӢгҒЈгҒҰгҖҒпҪўгҒӮгӮҢд»ҠгҒЈгҒҰ19дё–зҙҖгҒЁгҒӢ20дё–зҙҖгҒ гҒЈгҒ‘пјҹпҪЈгҒЈгҒҰжҖқгҒҶгҒҳгӮғгҒӘгҒ„гҒ§гҒҷгҒӢгҖӮгҒ§гӮӮгҒқгӮҢгҒҢгҖҒд»ҠгҒ“гҒ®21дё–зҙҖгҒ«гҒҫгҒҹзҸҫе®ҹгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖеғ•иҮӘиә«гҖҒиҮӘеҲҶгҒҢз”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢй–“гҒ«гҒ“гӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгҒҢиө·гҒҚгӮӢгҒӘгӮ“гҒҰгҖҒжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ§гҒҷгҖӮгҒ гҒ‘гҒ©гҖҒжӯҙеҸІгҒҜз№°гӮҠиҝ”гҒҷгҒЁгҒ„гҒҶгҒӢгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶеҒҙйқўгӮӮгҒӮгӮӢгӮ“гҒ§гҒҷгӮҲгҒӯгҖӮгҒ гҒӢгӮүйҒҺеҺ»гҒ«гҒ©гӮ“гҒӘдәӢдҫӢгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒӢгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдәәгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢгҖҒд»Ҡиө·гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гӮҲгӮҠж·ұгҒҸзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
_____йҒҺеҺ»гӮ’зҹҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒд»ҠгӮ’иҰӢгӮӢеҠӣгҒ«гӮӮгҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгӮ“гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ
гҖҖгҒқгӮҢгҒҜжң¬еҪ“гҒ«гҒқгҒҶгҒ§гҖӮеғ•гҒҜзҗҶи«–з ”з©¶гҒҢе°Ӯй–ҖгҒӘгӮ“гҒ§гҒҷгҒ‘гҒ©гҖҒзҗҶи«–з ”з©¶гҒЈгҒҰиЁҖгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒ„гҒҚгҒӘгӮҠй–ғгҒ„гҒҰеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҒҰгҖҒгӮ„гҒЈгҒұгӮҠе…·дҪ“зҡ„гҒӘжӯҙеҸІзҡ„дәӢдҫӢгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҒҰиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҸгӮӮгҒ®гҒӘгӮ“гҒ§гҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°д»ҠгҒ®гғӯгӮ·гӮўгғ»гӮҰгӮҜгғ©гӮӨгғҠжҲҰдәүгӮӮгҖҒжҺҲжҘӯгҒ§еӢүеј·гҒ—гҒҹзҗҶи«–гҒ§иӘ¬жҳҺгҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгҖҢгҒӮгҒ®зҗҶи«–гҒ§гҒ“гҒ®зҠ¶жіҒгҒЈгҒҰгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶйўЁгҒ«зҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгӮӢгӮ“гҒҳгӮғгҒӘгҒ„гҒӢгҖҚгҒЈгҒҰгҒ„гҒҶйўЁгҒ«гҒӯгҖӮгҒқгҒҶгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҖҒеӣҪйҡӣж”ҝжІ»еӯҰгӮ’еӯҰгҒ¶ж„Ҹзҫ©гҒҜгҒҷгҒ”гҒҸгҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
Q еӯҰз”ҹжҷӮд»ЈгӮ’жҢҜгӮҠиҝ”гҒЈгҒҰгҖҒе…Ҳз”ҹгҒҜгҒ©гӮ“гҒӘеӯҰз”ҹгҒ§гҒ—гҒҹгҒӢпјҹ
гҖҖгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮгҒӮгӮ“гҒҫгҖҢгӮөгғңгҒЈгҒҰгҒҫгҒ—гҒҹгҖҚгҒЁгҒӢиЁҖгҒҲгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҒӘгҒӮпјҲ笑пјүгҖӮеҘҪгҒҚгҒӘгҒ“гҒЁгҒ«гҒЁгҒ“гҒЁгӮ“еӨўдёӯгҒ«гҒӘгӮӢгӮҝгӮӨгғ—гҒ§гҒ—гҒҹгҒӯгҖӮгҒ гҒӢгӮүеҸ—йЁ“еӢүеј·гҒҜгҒқгӮҢгҒӘгӮҠгҒ«иӢҰеҠҙгҒ—гҒҹгҒ—гҖҒеӨ§еӯҰгҒ§гӮӮиӘһеӯҰгҒ®жҺҲжҘӯгҒЁгҒӢгҒҜжӯЈзӣҙиӢҰжүӢгҒ§гҖҒгҖҢи©ҰйЁ“еӨ§еӨүгҒ гҒӘпҪһгҖҚгҒЈгҒҰжҖқгҒ„гҒӘгҒҢгӮүгӮ„гҒЈгҒҰгҒҫгҒ—гҒҹпјҲ笑пјүгҖӮ
гҒ§гӮӮиҲҲе‘ігҒ®гҒӮгӮӢеҲҶйҮҺгҒ«гҒҜгҒҷгҒ”гҒҸзҶұдёӯгҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгҖҒжҺҲжҘӯгҒЁгҒҜй–ўдҝӮгҒӘгҒҸжң¬гӮ’иӘӯгӮ“гҒ гӮҠгҖҒиҮӘеҲҶгҒ§иӘҝгҒ№гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢеҘҪгҒҚгҒ§гҒ—гҒҹгҒӯгҖӮ

Q.еӨ§еӯҰз”ҹгҒ®гҒҶгҒЎгҒ«гӮ„гҒЈгҒҰгҒҠгҒ„гҒҹж–№гҒҢгҒ„гҒ„гҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢпјҹ
гҖҖгҒ“гӮҢгӮӮе®ҹгҒҜгҒӮгӮӢзЁ®гҒ®гғҮгӮЈгғ¬гғігғһгҒҢгҒӮгӮӢгӮ“гҒ§гҒҷгӮҲпјҲ笑пјүгҖӮгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гӮӮгҖҒеӯҰз”ҹгҒЈгҒҰгҒҠйҮ‘гҒҜгҒӮгӮ“гҒҫгӮҠгҒӘгҒ„гҒҳгӮғгҒӘгҒ„гҒ§гҒҷгҒӢпјҹгҒ§гӮӮгҖҒгҒқгҒ®д»ЈгӮҸгӮҠжҷӮй–“гҒҜгҒӮгӮӢгӮ“гҒ§гҒҷгӮҲгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒиӘІйЎҢгҒЁгҒӢгғҗгӮӨгғҲгҒ§еҝҷгҒ—гҒ„гҒЁгҒҜжҖқгҒҶгҒ‘гҒ©гҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮзӨҫдјҡдәәгҒЁжҜ”гҒ№гҒҹгӮүгҒҡгҒЈгҒЁиҮӘз”ұжҷӮй–“гҒҜеӨҡгҒ„гҖӮ
гҖҖйҖҶгҒ«зӨҫдјҡдәәгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒжҷӮй–“гҒҢгҒӘгҒҸгҒҰгҒҠйҮ‘гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®“жҷӮй–“гҒЁгҒҠйҮ‘гҒ®гғҲгғ¬гғјгғүгӮӘгғ•”гҒ«гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒҜзӨҫдјҡгҒ«еҮәгҒҰгҒӢгӮүж°—гҒҘгҒҸгӮ“гҒ§гҒҷгҖӮгҖҢгҒӮгҒ®й ғгҖҒгӮӮгҒЈгҒЁиҮӘз”ұгҒ«дҪҝгҒҲгӮӢжҷӮй–“гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮ“гҒ гҒӘгҒӮгҖҚгҒЈгҒҰгҖӮгҒ гҒӢгӮүгҒ“гҒқгҖҒеӯҰз”ҹжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜ“гҒҠйҮ‘гҒҢгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгҒ§гҒҚгӮӢжҘҪгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁ”гӮ’гҖҒгҒ©гӮ“гҒ©гӮ“гӮ„гҒЈгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒӘгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒӯгҖӮдҪ•гҒ§гӮӮгҒ„гҒ„гӮ“гҒ§гҒҷгҖӮеӢүеј·гҒ§гӮӮгҒ„гҒ„гҒ—гҖҒгӮөгғјгӮҜгғ«гҒ§гӮӮгҖҒж—…иЎҢгҒ§гӮӮгҖӮиҰҒгҒҷгӮӢгҒ«гҖҒгҖҢжҷӮй–“гҒҢгҒӮгӮӢд»ҠгҒ гҒӢгӮүгҒ“гҒқгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгӮ’гҖҒиҮӘеҲҶгҒӘгӮҠгҒ«гӮ„гҒЈгҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгҒ„гҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
.jpg)
———гӮӮгҒ—гҖҒе…Ҳз”ҹгҒҢ“1ж—ҘгҒ гҒ‘еӯҰз”ҹгҒ«жҲ»гӮҢгӮӢ”гҒЁгҒ—гҒҹгӮүпјҹ
гҖҖгҒқгӮҢгҒҜгҖҒе…ЁеҠӣгҒ§“д»•дәӢгҒ«й–ўдҝӮгҒӘгҒ„жң¬”гӮ’иӘӯгҒҝгҒҫгҒҸгӮҠгҒҫгҒҷгҒӯгҖӮд»ҠгӮӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“жң¬гҒҜиӘӯгӮ“гҒ§гӮӢгҒ‘гҒ©гҖҒгҒқгӮҢгҒҜгӮ„гҒЈгҒұгӮҠз ”з©¶гӮ„и«–ж–ҮгҒ®гҒҹгӮҒгҒ§гҖҒжҘҪгҒ—гҒ„гҒ‘гҒ©гҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁзҫ©еӢҷж„ҹгӮӮгҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҖӮ
гҒ гҒӢгӮүгҒ“гҒқгҖҒзҙ”зІӢгҒ«иҮӘеҲҶгҒ®иҲҲе‘ігҒ гҒ‘гҒ§е°ҸиӘ¬гҒЁгҒӢгӮ’ж°—гҒ®еҗ‘гҒҸгҒҫгҒҫгҒ«иӘӯгҒҝгҒҹгҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮгҒҠйҮ‘гӮ’гҒӢгҒ‘гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгҒ§гҒҚгӮӢгҖҒгҒ§гӮӮиҙ…жІўгҒӘжҷӮй–“гҒ®дҪҝгҒ„ж–№гҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғјпјҡй Ҳз”°гҖҖжҷҙиҸң