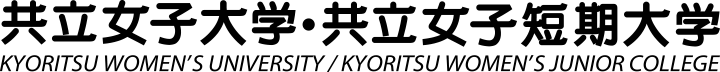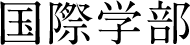Faculty of International Studies
国際学部取り組み・プロジェクト紹介 詳細
更新日:2018年11月07日
【国際学部】「アルザスの秋―百年の年月を越えて」(西山暁義)
アルザスの秋—百年の年月を越えて
西山 暁義
国際学部広報委員会のインスタグラムでも写真を掲載しましたが、10月の半ば、フランス・アルザス地方でヨーロッパにおける和解の歴史についてのシンポジウムがあり、報告のために出張してきました。
滞在したのはアルザス地方の中心都市ストラスブール。以前HPでも書いたように、2年ほど留学した際に暮らした、私にとってはヨーロッパの故郷のような街です。ただし、10月13日に開催されたシンポジウムのプログラム自体は市内ではなく、その郊外で開催されました。午前中は50 キロほど西、ヴォ―ジュ山脈の北部に位置する「アルザス・モーゼル記念館」という現代史博物館での見学。この博物館については、2014年の『共立女子大学・短期大学総合文化研究所紀要』、そして今年出版された論文集『越境する歴史認識―ヨーロッパにおける「公共史」の試み』(剣持久木編、岩波書店)で考察の対象にしており、記念館の関係者ともかれこれ10年近くのつき合いがあります。とくに「記念館友の会」の会長であるマルセル・スピセールさんとは、彼がこれも以前研究対象にしたことのある独仏共通歴史教科書のフランス側の学術委員会のメンバーであったこともあり、学校視察の斡旋や論文の執筆に当たっての情報提供、資料の貸し出しをしてもらったり、さらには2011年2月国際学部の研究旅行で訪問した際にガイドを買って出てもらったりと、いろいろとお世話になってきました(上述の論文集の表紙カバーの写真も記念館の写真です)。そして今回、彼から東アジアの視点からヨーロッパの和解について話してほしいという依頼があり、学期最中ではありましたが、これまでの恩返しということもあり、参加することにしました。
なお、アルザス・モーゼル記念館は、2016年秋から10ヵ月ほど改修増築のため休館し、昨年10月下旬に再開館となりました。今回の見学では、一部変更された従来の展示に加え、増築されたヨーロッパ統合についての展示を、スピセールさんの案内の下、30名ほどの参加者の方といっしょに見学することができました。これについては、ちょうど9月初めに同じような展示内容であるブリュッセルのヨーロッパ歴史館も見学してきたので、近くまた論文に書いてみようと考えています。
2018/10/13、記念館見学の前。私と向かい合っているのがスピセールさん。私の右隣は同じくパネリストとして参加したエティエンヌ・フランソワさん(パリ第一大学、ベルリン自由大学名誉教授)とその夫人ベアテさん。フランソワさんとは昨年論文集を出しました。
午後のシンポジウムの方は、同じヴォ―ジュ山脈をやや南に下った、標高762mの山上に立つモン・サントディールという修道院で行われました。この修道院は9世紀に設立されたとされ(現存の建物は17世紀以降のもの)、現在でも年間130万人もの巡礼者や見学者が訪れる、アルザス地方有数の観光地です。この場所で開催されたのは、シンポジウムがアルザス・モーゼル記念館と和解や交流を目的とするカトリックの団体との共催によるものであったからです。こちらには80人ほどの参加者が集まり、ドミニコ会の神父さんの司会の下、ヨーロッパ議会の議員、フランス、ドイツの歴史家とともに30分ほど喋り、そして他のパネリストやフロアの人たちとディスカッションをしてきました。
モン・サントディールでのシンポジウム。私は左から二人目。
モン・サントディーユは、すでに述べた通り、アルザスでは知らない人のいない「聖地」であり、私も訪問するのはこれで3回目のことでしたが、今回特別な感慨を持ったのは、ある日本の歴史家のことを思い浮かべていたからです。その名は坂口昂。1872年生まれで、東京帝国大学で西洋史を学び、京都帝国大学で教鞭をとった彼は、もちろん直接の面識など持ちようがありませんが、私にとってはほぼ1世紀(正確には97年)年上の大先輩に当たります。「お雇い外国人」のドイツの歴史家、ルードヴィヒ・リースの薫陶を受けた彼の研究は、古代ギリシャ・ローマやルネサンスなど、日本における西洋史研究の草創期世代の一人として、いわば「王道」のような時代を対象とするものでしたが、ヨーロッパ留学中の1911年、創設されたばかりの朝鮮総督府の委嘱によって、ドイツ帝国の東西の国境地域であるプロイセン領ポーランド(ポーゼン州)と、アルザス・ロレーヌ(エルザス・ロートリンゲン)の教育問題についての調査を行います。余計なことを書かれることを恐れたドイツ政府が学校視察を拒否するなか、坂口はアルザスを訪れ、持ち前の行動力を使って自力で資料を収集し、1913年に『ドイツ帝国境界地方の教育状況』と題する秘密報告書を総督府に提出します。この経緯については、以前ある論文集(平田雅博・原聖編『帝国・国民・言語—辺境という視点から』三元社、2017年)のなかで書いたことがあるので、詳細は省略します。
シンポジウム終了後、修道院の展望デッキから撮影。当日はご覧の通り快晴で、修道院からはライン川の向こうのドイツまで見渡せました。夕暮れ近く、山の影が差しています。
むしろ、ここでの感慨は、坂口が第一次世界大戦後、1922年にふたたびヨーロッパを訪れ、戦争によって大きく変わったヨーロッパの姿を記した紀行文『歴史家の旅から』(内外出版、1923年―1981年に中公文庫として再版されています。ただし以下の引用は原版から)の一節、「アルザスの秋」にかかわるものでした。タイトルからもわかるように、彼はこのとき、10年前に調査のために訪れたアルザスにも足を延ばしているのですが、そこで彼はドイツ領からフランス領に変わり、街路や広場、店の看板がドイツ語からフランス語に変わったストラスブールの姿を描いています。
ドイツ皇帝の離宮前の広場のカイゼル・プラッツ(皇帝広場―西山)が共和国広場(プラース・ド・ラ・レピュブリック)となっているのは尤もだ。大学附近に、かの有名なドイツの国法学者の名を負うたパウル・ラーバント河岸(スターデ)が今は全く違った人名のケー・ド・ルゼー・ド・リールと改まっている。これはいうまでもなく、かの有名なマルセイエーズの曲を作った、大革命当時このストラスブル(ママ)におけるフランス軍の陣中にいた青年士官だ。その名が採用されたのは良い思い付きだ。(p.358)
さらに、以前彼を温かく迎えてくれ、明治天皇(1912年)、昭憲皇太后(1914年)の崩御の際には哀悼の詩を送ったり、娘に着物を着せて和式の膳の前に小笠原式で座らせたという、親日家の友人「ドクトルT」なる高校の先生のことに筆は進みます。坂口は、再訪に当たって彼に手紙を送ったものの返事がなく、大戦で日本がドイツに宣戦布告したことに怒っているのだろうか、とか、戦後フランス領になり、ドイツ時代の公務員の多くが追放、退去させられたことから、この友人も同じ目に遭ってしまったのだろうか、などと考えを巡らせています。
その後、坂口はヴォ―ジュ山脈へと遠足に出かけるのですが、その目的地が他ならぬモン・サントディール(「聖オディル」)でした。そこで彼は、「聖セシリア唱歌組合」という地元の合唱協会がフランス語の歌ばかり歌っている一方、歌うメンバーたちの胸には、ドイツ時代の「ゲザンクフェルアイン・デル・ハイリゲン・チェチリーン」と刻まれた徽章がそのまま着用されていることに目をとめます。
モン・サントディールの修道院の中庭。合唱が行われていたのはおそらくここ。坂口が合唱団のメンバーと談笑したカフェ(レストラン)は奥の建物にあります。シンポジウムの会場は左側の建物。
合唱終了後、修道院の「カフェ」でビールが入った陽気な雰囲気のなか、坂口はメンバーの一人に問いかけます。
君たちの先刻謡ったのはフランスの歌だったね。それに君たちはまだ胸間にドイツ語の徽章をつけている。それでは時々はドイツの歌もうたうのかねと皮肉ったら、その青年は声高らかに揚言して、いや、いや、フランスの歌ばかりだ、語はフランス語に限る、フランス語程よい言葉はないからね、君もなんぞドイツ語をやめてフランス語を話さざると逆襲して来た。(p.366)
最後の発言から、彼らはドイツ語で会話していたことがわかりますが、このメンバーの、日本でも有名なアルフォンス・ドーデ『最後の授業』のアメル先生を彷彿とさせる発言の後、しばらく会話が途切れてしまいます。そこで別のメンバーが場を持たせようとして、自分の兄が(大戦時ドイツ人として)中国・青島で捕虜となった後帰国したが、日本はよい国だと褒めていたよ、と語ったのに対し、坂口は次のような感慨を記します。
私は尚更不幸なアルザシアン(アルザス人―西山)よと、衷心から彼らの罪もなく、意味もなく、只だ(ママ)国際間の風雲の動くままに漂わなければならぬ運命の悲しさに、一しほ(ママ)同情せずにはいられなかった。(同)
それから96年後の同じ季節、同じ場所、そしてほぼ同じ年齢(坂口50歳、私49歳)で、私は上述の通り、ヨーロッパの和解を東アジアの観点から話をすることになりました。坂口が感じた独仏国境地域の人びとの「運命の悲しさ」—といっても坂口が述べるように、アルザスの人びとはたんに独仏両国の狭間で弄ばれた国境の哀れな民というわけではなく、主体的で「したたかな」面も存在するのですが―は、両国の和解、ヨーロッパ統合のなかでたしかに克服されたといえるでしょう。昨年には、ストラスブールの路面電車が国境を越えドイツまでやってきました。これは第一次世界大戦後ライン川で路線が切断されて以来、100年ぶりのことです。そのための橋が加わり、今やストラスブールとドイツ側ケールの間には、鉄道、自動車、歩行者専用と合わせて4つ橋が間近に並んでおり、両国間の関係や交流の密度を象徴するかのようです。また、街路や広場の標識にも、ドイツ系の地域語が併記されたものが増えてきました。
(左)2017年開通した国境をまたぐ路面電車。ストラスブール側の最後の駅から撮影。奥の建物はドイツに立つ。
(右)歩行者専用の橋から撮影。奥には自動車用、さらにその奥には鉄道用、路面電車用の橋が並びます。左の写真の右側の高層アパートは上の写真の右端の建物と同一。
こうした現状を坂口がもし見ることができたなら、どのように感じたでしょうか。少なくとも「同情」の念は抱かなかったでしょう。もっとも、上述の街路のドイツ名からフランス名への改称を「尤もだ」とか「良い思い付きだ」と述べているように、彼も大正デモクラシーの時期に活躍したリベラルな歴史家とはいえ、ナショナリズムや帝国主義の時代の申し子でもあったので、「羨望」や「讃嘆」の念を抱いたかはわかりませんが、おそらく「仰天」はしただろうと思います。そして、当時と比べてはるかにフランス語が普及し、ドイツ語が後退していることに気が付いたことでしょう。たしかに今でもアルザス地方は、ドイツ語を話せる人がフランスの地方のなかでは断トツに多いのですが、それは必ずしも地域語(「方言」)がドイツ系だからというわけではなく、「川向う」の身近な外国語であり、キャリアにとっても重要な武器になるから、という面が強くなっているようです。第二次世界大戦直後、地域最大の新聞『デルニエール・ヌーヴェル・ダルザス』の購読者の大多数が読んでいたのはドイツ語版でしたが、その後減少が続き、2012年には廃止されてしまいました(オンライン上ではドイツ語の記事も閲覧できますが)。
これと比例するように、地域語についても、2012年の調査によれば、話者(話すことができる人)の割合は43%であり、1900年の推計値95%、第二次世界大戦直後の1946年の90.8%と比べると半分以下になっています。年齢別でも60歳以上が70%なのに対し、18~29歳の若年層では12%であり、地域語の未来は明るいものとは言えないのが現実です。つまり、フランスとドイツの間で争われたこの国境地方の戦後フランスへの言語的・文化的な同化が進み、そのフランスへの帰属が疑いないものとなるのと並行して、両国の和解と国境を越えた交流は進んでいったということになります。言い換えれば、「国境を越える」ためにはまず「国境を画定させる」ことが必要であったといえます。
シンポジウム後、山を下って、留学時代によく訪ねたワイン街道の美しい村、イッタースヴィラーのレストランで、スピセールさんたちと一緒に打ち上げの夕食をとりました。10年来の付き合いで、これまで何度も議論をしてきたこともあり、坂口のように皮肉を交えた会話にはなりませんでしたが、現在のヨーロッパ統合の動揺と戦争の記憶の問題、記念館の展示の批評などを語り合いながら、緊張から解放されたこともあり、大好きな地元の白ワイン、リースリングの芳醇な味わいを大いに楽しみました。
イッタースヴィラーのレストラン「アーノルド」。料理もワインも美味しかったです。右は駐車場からの(収穫の終わった)ぶどう畑の夕景。
坂口とは異なり、私の場合は友人たちとの再会も果たすことができました。私にとっての「ドクトルT」は二人いて、一人は地元アルザスの郷土史家であり、長年中学校の教師を務めてきたジャン=ピエール・イルシュさん(「ドクトルH」)。彼は小学校教師の奥さんとともにシンポジウムに顔を見せてくれました。もう一人は留学時代、よく公文書館で机を並べて史料を読みながら、お互いの発見を話し合ったドイツ人歴史家で現在シュツットガルト市公文書館職員のギュンター・リーデラーさん(「ドクトルR」)。彼はシンポジウムの翌日、ストラスブールの姉妹都市、シュツットガルトから会いに来てくれました。現在ヨーロッパが動揺しているにしても、平和が続いているからこそ、何度も訪れて再会を喜べるのだというありがたみを感じました。ちなみに坂口にとって、1922年の旅が最後のヨーロッパ訪問となり、1928年に彼は56歳の若さで急逝してしまいます。大先輩の歴史家の人生に勝手に自分を重ね合わせながら、私はあと何回訪れることができるだろうか―そんなことを考えながら、3日間の短い滞在を終え、ストラスブールを後にしました。
2018/10/14、ストラスブール大聖堂前のカフェのテラスで。フランソワ夫妻と大聖堂の日曜ミサに参列した後(私は曹洞宗徒)、リーデラーさんと合流。
なお、今回の出張では帰国の前に、せっかくなので最後にスイスのバーゼルのそばにあるドイツの町レラハの三国博物館を訪問・見学し、館長さんにインタビューをしてきました。これについてはまた別の記事で紹介したいと思います。