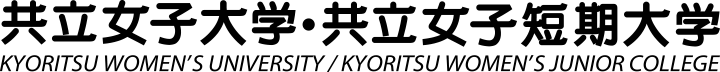卒業生インタビュー

子どもたちの小さな成長に
日々気づけることが今の喜び
家政学部 児童学科*(2023年度卒業)
勤務先:浦安市立猫実保育園 保育士
Q1 現在のお仕事の内容について詳しく教えてください。
1歳児クラスの担任をしています。子どもたちの生活リズムを考えながら、一緒に遊んで過ごしています。午前中は主活動の時間です。晴れている日は園庭遊びやお散歩、雨の日は室内遊びなど、日によって内容が異なります。その後給食を食べ、お昼寝をし、保護者の方がお迎えに来るまで遊んで過ごします。子どもたちが午睡をしている間は、個別指導計画を立てたり、連絡ノートを書いたりしています。1歳児になるとそれぞれ好きな遊びが決まってきて、積み木を高く積み上げることに夢中な子や、同じ絵本を繰り返し読んでほしがる子もいます。最近は粘土遊びが人気で、小麦粘土を使ってピザをつくったり、ちぎったりしています。また1歳は、子どもたちが急速に成長する時期です。自分でズボンが履けるようになったり、水道の蛇口が閉められるようになったりと、毎日関わっているからこそ、小さな成長に気づくことができます。昨日はできなかったことが、今日はできるようになっている。そんな子どもたちの成長を間近で見られるのが喜びです。子どもたちの成長を、一緒に働いている職員や保護者と共有できることにも幸せを感じます。毎朝保育室に行くと子どもたちが笑顔で出迎えてくれて、その瞬間にも「保育士になってよかった」と実感します。

Q2 大学での学びが現在のお仕事に活かされていることは何でしょうか。将来の目標についても教えてください。
実習はもちろん、普段の学校生活の中でも、実践的な学びを得ることができました。「保育・子育て実践演習」の授業では、「さくらんぼ※」の活動を通して1年間同じ親子と関わりました。さまざまな活動内容を考え、実践していく中で、実際の子どもの姿や発達を知ることができ、座学だけでは得られない学びを得ることができました。今後の目標は、先輩保育士のようになることです。子どもたちのありのままの姿を受け止め、保育者の私が今子どもたちにできることは何かを常に考えていきたいと思っています。また、子どもだけでなく保護者にも寄り添い、保育園に通う子どもとその保護者が安心できる場所であるよう努めていきたいです。

Q3 共立女子大学、児童学科の魅力は何だと思われますか。
共立女子大学では、たくさんの素敵な友人や先生、職員さんと出会うことができました。そうした方々から「あなたならできる」と言ってもらい、信じてもらっていたからこそ、保育士としての今の私があると思っています。共通の夢を持つ仲間と出会い、実習や就職活動など、大変なことも励まし合って一緒に頑張ったことは大切な思い出です。
Q4 特に今のあなたの礎となった共立女子大学での経験や体験をお聞かせください。
乳児保育を専門とする、守随先生の授業を受けたことです。乳児に対しては、「あなたを好きな大人はいっぱいいるんだよ」と感じてもらうことが重要であり、その体験によって、他者に愛情を注げる人が育まれるという内容でした。この話を聞いて、「子どもたちのありのままの姿を受け止められる先生になりたい」という軸が固まっていきました。
※子どもたちとその保護者が、児童学科の教員・学生と共にゆったりと遊ぶグループ活動
*2026年4月、児童学部 児童学科に改組(設置構想中)
(2025年2月掲載)