
Faculty of International Studies
еӣҪйҡӣеӯҰйғЁгғӢгғҘгғјгӮ№и©ізҙ°
жӣҙж–°ж—Ҙпјҡ2025е№ҙ01жңҲ10ж—Ҙ
еӯҰз”ҹгҒ®жҙ»еӢ•
гҖҗеӣҪйҡӣеӯҰйғЁгҖ‘еӯҰз”ҹеәғе ұ委員дјҡгҒ«гӮҲгӮӢиӘІйЎҢи§ЈжұәгғҜгғјгӮҜгӮ·гғ§гғғгғ—и¬ӣжј”дјҡгғ¬гғқгғјгғҲ
гҖҖгҒҝгҒӘгҒ•гӮ“гҖҒгҒ“гӮ“гҒ«гҒЎгҒҜгҖӮеӣҪйҡӣеӯҰйғЁеәғе ұ委員дјҡгҒ®жӨҺеҗҚжІҷз·’зҗҶгҖҒеҗүз”°йҷҪе’ІгҖҒеҶ…и—ӨзҫҺе’ІгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖ11жңҲ21ж—ҘгҒ«з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜиӘІйЎҢи§ЈжұәгғҜгғјгӮҜгӮ·гғ§гғғгғ—гҒ®и¬ӣжј”дјҡгҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮд»ҠеӣһгҒҜеӨ–еӢҷзңҒгҒ«й•·е№ҙеӢӨеӢҷгҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҹиҘҝжһ—дёҮеҜҝеӨ«е…Ҳз”ҹгӮ’гҒҠжӢӣгҒҚгҒ—гҖҒжө·еӨ–гҒ§гҒ®гҒҠд»•дәӢгҒ®гҒҠи©ұгӮ„ж–ҮеҢ–дәӨжөҒгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®гҒҠи©ұгӮ’иҒһгҒӢгҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖиҘҝжһ—дёҮеҜҝеӨ«е…Ҳз”ҹгҒҜеӨ–еӢҷзңҒгҒ«й•·е№ҙеӢӨеӢҷгҒ•гӮҢгҖҒеӨ–еӣҪгҒ§32е№ҙй–“еғҚгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиЁӘгӮҢгҒҹеӣҪгҒ®ж•°гҒҜ80гҒӢеӣҪд»ҘдёҠгҒҫгҒ§дёҠгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠеӨ–еӣҪгҒ§гҒҜж—Ҙжң¬гҒ®еәғе‘ҠеЎ”гҒЁгҒ—гҒҰж—Ҙжң¬гҒ®ж–ҮеҢ–гӮ’дјқгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«ж§ҳгҖ…гҒӘж–ҮеҢ–дәӨжөҒгҒ®гӮӨгғҷгғігғҲгӮ’иЎҢгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮжІ»е®үгҒ®жӮӘгҒ„еӣҪгҒ§еғҚгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹйҡӣгҒҜгғңгғҮгӮЈгғјгӮ¬гғјгғүгӮ’гҒӨгҒ‘гҒҰжӯ©гҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒҠи©ұгӮ’гҒҠиҒһгҒҚгҒ—гҖҒеӨ–еӣҪгҒ§еғҚгҒҸйӣЈгҒ—гҒ•гӮӮж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҢгӮҜгғјгғ«гӮёгғЈгғ‘гғіжӢ…еҪ“еӨ§иҮЈгҖҚгӮ„JETгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒӘгҒ©з§ҒгҒҹгҒЎгҒҢжҷ®ж®өиҖігҒ«гҒ—гҒӘгҒ„ж–ҮеҢ–дәӨжөҒгҒ®гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®иӘ¬жҳҺгӮӮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гғ‘гғ–гғӘгғғгӮҜгғ»гғҮгӮЈгғ—гғӯгғһгӮ·гғј
гҖҖдјқзөұзҡ„гҒӘеӨ–дәӨй–ўдҝӮгҒҜгҖҒж”ҝеәңгҒЁж”ҝеәңгҒҢеӣҪгӮ’д»ЈиЎЁгҒ—гҒҰдәӨжёүгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгғ‘гғ–гғӘгғғгӮҜгғ»гғҮгӮЈгғ—гғӯгғһгӮ·гғјгҒҜгҖҒд»–гҒ®еӣҪгҒ®дәәйҒ”гҒ«гҖҒиҮӘеҲҶгҒ®еӣҪгҒ®ж–ҮеҢ–гӮ„ж”ҝзӯ–гӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒҶдәӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиҮӘеҲҶйҒ”гҒ®еӣҪгҒ®еҲ©зӣҠгҒ«з№ӢгҒҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҒ®ж–°гҒ—гҒ„еӨ–дәӨгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖгҒқгҒ®йЎһеһӢгҒЁгҒҜгҖҒж”ҝзӯ–еәғе ұгҖҒпјҲзӢӯзҫ©гҒ®пјүж–ҮеҢ–еӨ–дәӨгҖҒдәәзҡ„дәӨжөҒеӨ–дәӨпјҲJETгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒЁиЁҖгҒЈгҒҰеӨ–еӣҪгҒӢгӮүеӨ§еӯҰз”ҹгӮ’е‘јгӮ“гҒ§иӢұиӘһгӮ’ж•ҷгҒҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒӘгҒ©пјүгҖҒеӣҪйҡӣе ұйҒ“пјҲгғЎгғҮгӮЈгӮўгӮ’йҖҡгҒҳгҒҹPRпјүгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖеҶ·жҲҰеҫҢгҒ«гҒҜгҖҒгӮ°гғӯгғјгғҗгғ«гҒӘиҰҸжЁЎгҒ§ж”ҝжІ»зөҢжёҲзөұеҗҲгӮ„еқҮиіӘеҢ–гҒҢйҖІгҒҝгҖҒгӮҪгғ•гғҲгғ‘гғҜгғјпјҲеӣҪгҒ®йӯ…еҠӣгӮ’дјқгҒҲгӮӢеҠӣпјүгӮӮйҮҚиҰҒиҰ–гҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҖҢгӮҪгғ•гғҲгғ‘гғҜгғјгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгӮ’еәғгӮҒгҒҹгғҸгғјгғҗгғјгғүеӨ§еӯҰгҒ®е…Ҳз”ҹгӮӮгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гӮҪгғ•гғҲгғ‘гғҜгғјгӮ’и©•дҫЎгҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиҝ‘е№ҙSNSгӮ’дҪҝгҒЈгҒҹж–ҮеҢ–дәӨжөҒгҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҫ“жқҘеһӢгҒ®ж–ҮеҢ–дәӨжөҒгҒЁгғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүејҸгҒ«гҒҷгӮӢдәӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжӣҙгҒӘгӮӢж–ҮеҢ–дәӨжөҒдҝғйҖІгӮ’еӣігҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ®ж–ҮеҢ–еӨ–дәӨ
гҖҖ1873е№ҙгҒ®гӮҰгӮЈгғјгғігҒ®дёҮеҚҡгҒ§гҒҜгҖҒеӨ§йҡҲйҮҚдҝЎгҒҢгғҲгғғгғ—гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰжә–еӮҷгҒ—гҖҒеӣҪ家дәҲз®—гҒ®1еүІгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰжө®дё–зөөгӮ„е·ҘиҠёе“ҒгӮ’еҮәеұ•гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҢгӮёгғЈгғқгғӢгӮәгғ гҖҚгҒҢеәғгҒҫгӮҠгҖҒжө·еӨ–гҒ®дәәгҖ…гҒ®ж—Ҙжң¬гҒёгҒ®й–ўеҝғгҒҢеј·гҒҫгҒЈгҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒеӣҪйҡӣж–ҮеҢ–жҢҜиҲҲдјҡгҖҒгғҰгғҚгӮ№гӮіеҠ зӣҹгҖҒеӣҪйҡӣдәӨжөҒеҹәйҮ‘иЁӯз«ӢгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒҜгҖҒж–ҮеҢ–еӨ–дәӨгӮ’йҖІгӮҒгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖгҒҫгҒҹгҖҒгҖҢж–ҮеҢ–дәӨжөҒгӮ’еј·еҢ–гҒҷгӮӢдәӢгҒҢж—Ҙжң¬гҒ®е®үе…ЁдҝқйҡңгҒ«зөҗгҒігҒӨгҒҸгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲгҒҢеәғгҒҫгӮҠгҖҒгҒ•гӮүгҒ«ж—Ҙжң¬еҗ„ең°гҒ®иҮӘжІ»дҪ“гҒ§гӮӮеӣҪйҡӣдәӨжөҒжҙ»еӢ•гҒҢжҙ»жҖ§еҢ–гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒ2009е№ҙгҒ«гҖҒж°‘дё»е…ҡж”ҝжЁ©гҒҢе®ҹж–ҪгҒ—гҒҹгҖҢд»•еҲҶгҒ‘дәӢжҘӯгҖҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеӣҪйҡӣдәӨжөҒгҒ®дәҲз®—гҒҢеӨ§е№…гҒ«еүҠгӮүгӮҢгҒҹдәӢгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮд»ҠеҫҢгҒ®иӘІйЎҢгҒҜгҖҒгӮўгӮҜгӮҝгғјй–“гҒ®йҖЈжҗәгӮ’еј·еҢ–гҒҷгӮӢдәӢгҒЁгҖҒж°‘й–“гӮӮж–ҮеҢ–дәӨжөҒгҒ®жӢ…гҒ„жүӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒз©ҚжҘөзҡ„гҒ«жҙ»еӢ•гҒҷгӮӢдәӢгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖиҘҝжһ—е…Ҳз”ҹгҒҜгҖҒ16дё–зҙҖгҒӢгӮүжҲҰеҫҢгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҒ®гҖҒж—Ҙжң¬гҒЁгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®ж–ҮеҢ–дәӨжөҒгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®жӯҙеҸІгӮӮи©ұгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®дёӯгҒ§еҚ°иұЎгҒ«ж®ӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬дәәгҒҢеҲқгӮҒгҒҰгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гӮ’иЁӘгӮҢгҒҹе ҙжүҖгҒҢгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®гғӯгғјгғһгҒ гҒЈгҒҹгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒЁгҖҒж—Ҙжң¬ж”ҝеәңгҒҢгҖҒж—Ҙжң¬ж–ҮеҢ–гӮ’жҷ®еҸҠгҒ•гҒӣгӮӢзӣ®зҡ„гҒ§еҲқгӮҒгҒҰжө·еӨ–гҒ«иЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹж–ҪиЁӯгҒҢгҖҒгғӯгғјгғһж—Ҙжң¬ж–ҮеҢ–дјҡйӨЁгҒ гҒЈгҒҹгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒЁж—Ҙжң¬гҒ«гҒҜгҖҒеҸӨгҒҸгҒӢгӮүйҮҚиҰҒгҒӘй–ўгӮҸгӮҠгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖгҒҫгҒҹгҖҒйЈҹгҒ«дҝқе®Ҳзҡ„гҒӘгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ§й–ӢгҒӢгӮҢгҒҹгҖҒдё–з•ҢеҲқгҒ®гҖҢйЈҹгҖҚгҒ®дёҮеҚҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖҒгғҹгғ©гғҺгғ»йЈҹгҒ®дёҮеҚҡпјҲ2015пјүгҒ«гҒҰж—Ҙжң¬гҒҢйҮ‘иіһгӮ’еҸ—иіһгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒж—Ҙжң¬йЈҹгҒҢгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜдё–з•ҢгҒ«еәғгҒҫгӮӢгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮи©ұгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮӘгғӘгғігғ”гғғгӮҜгӮ„дёҮеҚҡгҒӘгҒ©гҒҜгҖҒеӣҪгҒ®ж–ҮеҢ–гӮ„дјқзөұгӮ’PRгҒҷгӮӢдёҠгҒ§гҒЁгҒҰгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘгӮӨгғҷгғігғҲгҒЁгҒӘгӮӢгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖж—Ҙжң¬дәәгҒҢгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ»гҒ©гҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәгҒҜж—Ҙжң¬гҒ®гҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁд»°гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮж—Ҙжң¬гҒӢгӮүгҒ®гӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ«ж—…иЎҢгҒҷгӮӢдәәгҒҜгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒӢгӮүж—Ҙжң¬гҒёж—…иЎҢгҒ«жқҘгӮӢдәәгӮҲгӮҠгӮӮеӨҡгҒҸгҖҒгӮўгғігғҗгғ©гғігӮ№гҒҢз”ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖ2013е№ҙгҒӢгӮү17е№ҙгҒҫгҒ§еңЁгӮ®гғӘгӮ·гғЈеӨ§дҪҝгӮ’гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹиҘҝжһ—е…Ҳз”ҹгҒҜгҖҒдҪіеӯҗеҶ…иҰӘзҺӢж®ҝдёӢгҒ®гӮ®гғӘгӮ·гғЈгҒ”иЁӘе•ҸпјҲ2024е№ҙ5жңҲ25ж—ҘгҒӢгӮү8ж—Ҙй–“пјүгҒ®йҡӣгҒ«йҡҸиЎҢгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиҘҝжһ—е…Ҳз”ҹгҒҜгҖҒдҪіеӯҗж§ҳгҒҢгҒ”иЁӘе•ҸгҒ•гӮҢгӮӢеҖҷиЈңең°гӮ’йҒёгҒ°гӮҢгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒжә–еӮҷгҒ«гӮӮжҗәгӮҸгҒЈгҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҖҒгғ•гӮЎгғҚгғӯгғЎгғӢдҝ®йҒ“йҷўгӮ„гҖҒгӮўгӮёгӮўзҫҺиЎ“йӨЁпјҲгӮұгғ«гӮӯгғ©еі¶пјүгҒёгҒ”иЁӘе•ҸгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹзөҢз·ҜгӮ’и©ұгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖдҪіеӯҗеҶ…иҰӘзҺӢж®ҝдёӢгҒ®гӮ®гғӘгӮ·гғЈгҒ”иЁӘе•ҸгҒ§гҒҜгҖҒжң¬еӯҰеҗҚиӘүж•ҷжҺҲгҒ®жңЁжҲёйӣ…еӯҗе…Ҳз”ҹгҒҢгҒ”йҖІи¬ӣгҖҒзҸҫең°гҒ§гҒ®и§ЈиӘ¬гӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮд»ҘдёӢгҒ®URLгӮҲгӮҠй–ўйҖЈиЁҳдәӢгӮ’гҒҠиӘӯгҒҝгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗеӣҪйҡӣеӯҰйғЁгҖ‘жңЁжҲёйӣ…еӯҗеҗҚиӘүж•ҷжҺҲгҒҢз§ӢзҜ е®®дҪіеӯҗеҶ…иҰӘзҺӢж®ҝдёӢгҒ®гӮ®гғӘгӮ·гғЈиЁӘе•ҸгҒ«йҡӣгҒ—гҖҒгҒ”йҖІи¬ӣгҖҒзҸҫең°гҒ§гҒ®и§ЈиӘ¬гӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/academics/undergraduate/kokusai/news/detail.html?id=4856
гҖҖиҘҝжһ—е…Ҳз”ҹгҒҜгҖҒд»ҠеӣһгҒ®и¬ӣжј”дјҡгҒ®гҒҫгҒЁгӮҒгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒж–ҮеҢ–еӨ–дәӨгҒҜгҒҷгҒҗгҒ«еҠ№жһңгҒҢгҒ§гӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒе…ҲгӮ’иҰӢгҒҰжҲҰз•ҘгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮ„гҖҒй•·гҒ„еҠӘеҠӣгӮ’з¶ҡгҒ‘гҖҒиҰӘж—Ҙ家гӮ’иӮІгҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еӨ§еҲҮгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁд»°гҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒж·ұгҒҸж„ҹйҠҳгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖжңҖеҫҢгҒ®иіӘз–‘еҝңзӯ”гҒ®жҷӮй–“гҒ§гҒҜгҖҒгҖҢд»ҠгҒҫгҒ§пјҲгҒ®еӨ–дәӨе®ҳгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®жҙ»еӢ•гҒ®гҒӘгҒӢпјүгҒ§гҖҒдёҖз•ӘеҚ°иұЎгҒ«ж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгӮ“гҒ§гҒҷгҒӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиіӘе•ҸгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒи¶Је‘ігҒ§ејҫгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгғҙгӮЎгӮӨгӮӘгғӘгғігӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҖҒж»һеңЁе…ҲгҒ§гғҒгғЈгғӘгғҶгӮЈгғјжј”еҘҸдјҡгҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҖҒд»•дәӢд»ҘеӨ–гҒ®е ҙйқўгҒ§гӮӮгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гӮӨгғЎгғјгӮёгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢжҙ»еӢ•гҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒ“гҒЁгҒ гҒЁзӯ”гҒҲгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжң¬жҘӯгҒ®гҒҠд»•дәӢд»ҘеӨ–гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гӮӮгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еӨ–дәӨгҒ«иІўзҢ®гҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гӮӢж–№гҒҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еӨ§дҪҝгӮ’гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҖҒйқһеёёгҒ«ж„ҹжҝҖгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖд»ҠеӣһгҒ®и¬ӣжј”гҒ§гҒҜгҖҒж–ҮеҢ–еӨ–дәӨгҒ®йҮҚиҰҒжҖ§гӮ„гҒқгҒ®еҪұйҹҝгҒҢгҖҒжӯҙеҸІгӮ’иҫҝгӮҠй•·жңҹзҡ„гҒӘиҰ–зӮ№гҒ§жҚүгҒҲгӮүгӮҢгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮиүҜгҒ„еӯҰгҒігҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиҘҝжһ—е…Ҳз”ҹгҒ®е®ҹдҪ“йЁ“гӮ’дәӨгҒҲгҒҹгҒҠи©ұгҒҜгҒЁгҒҰгӮӮиҲҲе‘іж·ұгҒҸгҖҒзү№гҒ«ж–ҮеҢ–дәӨжөҒгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰж—Ҙжң¬гҒ®йӯ…еҠӣгӮ’дјқгҒҲгӮҲгҒҶгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒқгҒ®еҠӘеҠӣгҒ«ж„ҹжҝҖгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиІҙйҮҚгҒӘгҒҠжҷӮй–“гӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒҠи©ұгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
в—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Үв—Ҷв—Ү
↓↓гҖҖGSEгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ зү№иЁӯгӮөгӮӨгғҲгҒҜд»ҘдёӢгҒӢгӮүгҒ”иҰ§гҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒҫгҒҷгҖҖ↓↓
↓↓гҖҖеӣҪйҡӣеӯҰйғЁгҒ®жғ…е ұгҒҜд»ҘдёӢгҒӢгӮүгӮӮгҒ”иҰ§гҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒҫгҒҷгҖҖ↓гҖҖ

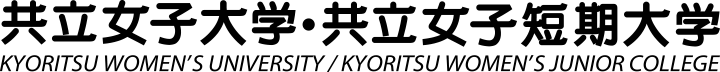




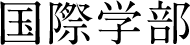
.jpg)
.jpg)