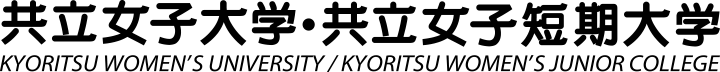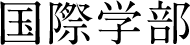Faculty of International Studies
еӣҪйҡӣеӯҰйғЁгғӢгғҘгғјгӮ№и©ізҙ°
жӣҙж–°ж—Ҙпјҡ2025е№ҙ10жңҲ10ж—Ҙ
еӯҰз”ҹгҒ®жҙ»еӢ•
гҖҗеӣҪйҡӣеӯҰйғЁгҖ‘жүӢд»•дәӢгӮ’гӮҒгҒҗгӮӢж—…пҪһгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўж—…иЎҢиЁҳпҪһв‘Ў
еӯҰз”ҹеәғе ұ委員2е№ҙз”ҹгҒ®иҘҝз”°еҖ«еӯҗгҒ•гӮ“гҒҢгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еүҚгҒ®иЁҳдәӢгҒҜгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮүгҒ”иҰ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гғјгғјгғјгғјгғјгғјгғјгғјгғјгғј
3.еҗ„йғҪеёӮгғ¬гғқгғјгғҲ
в‘ йҰ–йғҪTallinn(гӮҝгғӘгғі)

гҖҗгӮҝгғӘгғігҒЁгҒҜпјҹгҖ‘
гҖҖгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ®йҰ–йғҪгҒ§гҖҒиЎҢж”ҝгӮ„зөҢжёҲгҒ®дёӯеҝғең°гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдёӯдё–жҷӮд»ЈгҒӢгӮүеҪ“жҷӮгҒ®гҒҫгҒҫзҸҫеӯҳгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ1997е№ҙгҒ«дё–з•ҢйҒәз”ЈгҒ«зҷ»йҢІгҒ•гӮҢгҒҹж—§еёӮиЎ—гҒЁгҖҒе•ҶжҘӯж–ҪиЁӯгӮ„дјҡзӨҫгҖҒз©әжёҜгӮ„й§…гҒӘгҒ©гҒҢдёҰгҒ¶зҸҫд»ЈгҒ®иЎ—пјҲж–°еёӮиЎ—пјүгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮж—§еёӮиЎ—гҒҜгҒӢгҒӨгҒҰгҒҜдёӯдё–жҷӮд»ЈгҖҒзҸҫеңЁгҒ®гӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒҢгғӘгғҙгӮ©гғӢгӮўйЁҺеЈ«еӣЈй ҳгҒ гҒЈгҒҹжҷӮгҒ«з¬¬дәҢгҒ®жёҜз”әгҒЁгҒ—гҒҰж „гҒҲгҖҒгҒқгҒ®еҫҢ1154е№ҙгҒ«гҖҒгғҮгғјгғідәә*1зҺӢгғҙгӮЎгғ«гғҮгғһгғјгғ«пј’дё–гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҫҒжңҚгҒ•гӮҢгҒҹгӮҠгҖҒеҲҘгҒ®йЁҺеЈ«еӣЈгҒ®ж”Ҝй…ҚдёӢгҒ«зҪ®гҒӢгӮҢгӮӢгҒ”гҒЁгҒ«з”әгҒ®е»әиЁӯгӮ„йҳІеӮҷгҒҢйҖІгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҖӮдёӯдё–жҷӮд»ЈгҒ«гҒҜгғҸгғігӮ¶еҗҢзӣҹгӮ’зөҗгҒігҖҒеҢ—гғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ®е•ҶжҘӯеңҸгҒ®дёҖгҒӨгҒ®дәӨжҳ“жӢ зӮ№гҒЁгҒ—гҒҰж „гҒҲгҒҹгҖӮTallinnпјҲгӮҝгғӘгғіпјүгҒЁгҒҜгҖҒгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўиӘһгҒ§гҖҢгғҮгғјгғідәәгҒ®з”әгҖҚвӢҶ2гҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖжіЁ1)гҖҖгғҮгғјгғідәәпјҡпјҳпҪһ11дё–зҙҖгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҹгғҙгӮЎгӮӨгӮӯгғігӮ°гҒ®дёӯгҒ§гӮӮгҖҒзҸҫеңЁгҒ®гғҮгғігғһгғјгӮҜгӮ’жң¬жӢ гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹдәәгҖ…гҖӮ
гҖҖжіЁ2)гҖҖ“Taani linn” пјҲгӮҝгғјгғӢгғӘгғіпјүгҖҖгҒҢзңҒз•ҘгҒ•гӮҢгҒҰ”TallinnпјҲгӮҝгғӘгғіпјүгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖ”Taani“гҒҜгҖҒзҸҫеңЁгӮӮгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўиӘһгҒ§гҖҢгғҮгғігғһгғјгӮҜгҖҚгҖҒ”linn”гҒҜгҖҢз”әгҖҚгӮ’жҢҮгҒҷгҖӮ
гғ»ж—§еёӮиЎ—
гҖҖжңҖеҲқгҒ«гҖҒж°—еҖҷгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ2024е№ҙ11жңҲгҒ®жқұдә¬гҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®жҷӮжңҹгҒ«19в„ғгҒ§дҫӢе№ҙгӮҲгӮҠжҡ–гҒӢгҒ„гҒӘгҒ©гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ§гҒҜ3в„ғгҒ—гҒӢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жҷӮгҖҒжүӢиўӢгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹзӮәгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠгҒ®еҜ’гҒ•гҒ«жүӢгӮ’еӢ•гҒӢгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ2025е№ҙ6жңҲгҒ«иЁӘгӮҢгҒҹжҷӮгҒҜгҖҒжңқгҒҜ12в„ғзЁӢгҒ§жҳјгҒ§гӮӮ15в„ғеүҚеҫҢгҒ гҒЈгҒҹгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒй•·иў–еҝ…й ҲгҒ§ж—Ҙжң¬гӮҲгӮҠеҜ’гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮеӨҸгҒ®гӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒҜж—Ҙжң¬гҒЁйҒ•гҒ„гҖҒеёёгҒ«д№ҫзҮҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжҷҙгӮҢгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°ж—Ҙе·®гҒ—гҒҢеј·гҒ„гҒҹгӮҒгҖҒж°—жё©гҒҢ20в„ғеүҚеҫҢгҒ§гӮӮж—Ҙеҗ‘гҒҜжҡ‘гҒ„гҖӮеҶ¬гҒҜж—ҘгҒҢиҗҪгҒЎгӮӢгҒ®гҒҢж—©гҒҸгҖҒеӨҸгҒҜеӨңгҒ§гӮӮжҳҺгӮӢгҒ„гҖӮ
.jpg)
гҖҖж—§еёӮиЎ—гҒ«гҒҜиІҙж—ҸгҒҢдҪҸгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҖҢдёҠгҒ®з”әгҖҚгҒЁгҖҒеә¶ж°‘гӮ„е•Ҷе·ҘжҘӯиҖ…гҒҢдҪҸгҒҝгҖҒж§ҳгҖ…гҒӘеә—гҒҢз«ӢгҒЎдёҰгҒ¶гҖҢдёӢгҒ®з”әгҖҚгҒЁгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҖҢдёҠгҒ®з”әгҖҚгҒ«гҒҜзҸҫеңЁгҒҜеӣҪдјҡиӯ°дәӢе ӮгӮ„ж”ҝеәңй–ўдҝӮиҖ…ж–ҪиЁӯгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеҺігҒӢгҒӘйӣ°еӣІж°—гҒҢжјӮгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮж—§еёӮиЎ—гҒ«гҒҜж§ҳгҖ…гҒӘиҲҲе‘іж·ұгҒ„е»әзү©гҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒзү№гҒ«еҚ°иұЎгҒ«ж®ӢгҒЈгҒҹиҒ–гғӢгӮігғ©гӮ№ж•ҷдјҡгӮ’зҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҖӮ
в—ҸNiguliste Kirik(иҒ–гғӢгӮігғ©гӮ№ж•ҷдјҡ)
гҖҖж—§еёӮиЎ—гҒ®дёӯгҒ§гҒҜгҖҒе”ҜдёҖгҖҒгӮЁгғ¬гғҷгғјгӮҝгғјгҒ§дёҠгҒ«дёҠгӮҢгӮӢ“ж•ҷдјҡ”гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе…ғгҖ…гҒҜж•ҷдјҡгҒЁгҒ—гҒҰе»әгҒҰгӮүгӮҢгҒҹгҒҢгҖҒзҸҫеңЁгҒҜзҫҺиЎ“йӨЁгӮ„еұ•жңӣеҸ°гҒЁгҒ—гҒҰдҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖе…Ҙе ҙж–ҷгҒҜдёҖиҲ¬гҒ§15€гҒ§еӯҰз”ҹгҒҢпјҷ€гҖӮгҒҹгҒҫгҒҹгҒҫжҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹеӨ§еӯҰгҒ®еӯҰз”ҹиЁјгҒҢгҒ“гӮ“гҒӘжүҖгҒ§еҪ№гҒ«з«ӢгҒЈгҒҹгҖӮе»әзү©еҶ…гҒ«гҒҜгҖҒ14дё–зҙҖгҒ«гғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ§жөҒиЎҢгҒЈгҒҹй»’жӯ»з—…пјҲгғҡгӮ№гғҲпјүгҒӢгӮүжӯ»гҒ®жҒҗжҖ–гӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢе…ұйҖҡжҖ§гӮ’иЎЁзҸҫгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢжӯ»гҒ®гғҖгғігӮ№гҖҚпјҲдҪңиҖ…:гғӘгғҘгғјгғҷгғғгӮҜгҒ®з”»е®¶Bernt Notke,15дё–зҙҖеҫҢеҚҠпјүе®—ж•ҷзҡ„гҒӘгғ‘гғҚгғ«гҒӘгҒ©гҒҢеұ•зӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
.jpg)
.jpg)
гғ»MardiLaat(гғһгғ«гғҮгӮЈгғ©гғјгғҲ)
гҖҗгғһгғ«гғҮгӮЈгғ©гғјгғҲгҒЁгҒҜпјҹгҖ‘
гҖҖгӮҝгғӘгғігҒ§жҜҺе№ҙ11жңҲгҒ«й–ӢеӮ¬гҒ•гӮҢгӮӢеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘжүӢе·ҘиҠёеёӮе ҙгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҒгӮұгғғгғҲгҒ«ж’®еҪұзҰҒжӯўгҒ®иЎЁзӨәгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹзӮәж®ӢеҝөгҒӘгҒҢгӮүеҶҷзңҹгҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҒҢгҖҒгӮўгғӘгғјгғҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеәғгҒ„дјҡе ҙеҶ…гҒ«ж§ҳгҖ…гҒӘжүӢе·ҘиҠёиҖ…гҒ®гғ–гғјгӮ№гҒҢдёҰгҒігҖҒеҪјгӮүгҒ®дҪңе“ҒгӮ„гҖҒжүӢиҠёгҒ®жқҗж–ҷгҒӘгҒ©гӮ’иіје…ҘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгҒҹгӮҠгҖҒгғҜгғјгӮҜгӮ·гғ§гғғгғ—гҒ«еҸӮеҠ гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгӮӢгҖӮжүӢе·ҘиҠёгҒҜгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгҒ®ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ«гҒҫгҒӨгӮҸгӮӢгӮӮгҒ®гӮ„гҖҒзҸҫд»Јзҡ„гҒӘжүӢиҠёдҪңе“ҒгҖҒгӮўгӮҜгӮ»гӮөгғӘгғјгҒҫгҒ§е№…еәғгҒҸиҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзқҖгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮ№гғҶгғјгӮёгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒжҷӮгҖ…гғҖгғігӮ№гӮ„жӯҢгҖҒеҠҮгҒӘгҒ©гҒҢжҠ«йңІгҒ•гӮҢиҮӘз”ұгҒ«иҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгӮӢгҖӮ
гҖҖз§ҒгҒҜеҗ„гғ–гғјгӮ№гӮ’е‘ЁгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒж°‘и¬ЎгҒ®гӮ№гғҶгғјгӮёгӮ’жҘҪгҒ—гӮ“гҒ гӮҠгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒPärnu(гғ‘гғ«гғҢ)ең°ж–№гҒ®ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ®жң¬гҒЁгҖҒгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўеҗ„ең°гҒ®еҘіжҖ§гҒ®ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ®й ӯйЈҫгӮҠгӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢжң¬гҖҒHiiumaa(гғ’гғјгӮҰгғһгғјеі¶)гҒ®Pühalepa(гғ—гғҸгғ¬гғ‘)ең°еҹҹгҒ®ж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ®гӮ№гӮ«гғјгғҲгҒ®жҹ„гҒ®зҙ°й•·гҒ„еёғгӮ’иіје…ҘгҒ—гҒҹгҖӮ

.jpg)
гғ—гғҸгғ¬гғ‘гҒ®гӮ№гӮ«гғјгғҲжҹ„гҒ®еёғгҒЁгҖҒж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…гҒ®дәәеҪў(гғһгғ«гғҮгӮЈгғ©гғјгғҲгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸз©әжёҜгҒ§иіје…ҘгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҒҢгҖҒ
еҸӮиҖғзЁӢеәҰгҒ«гҖӮ)
ж¬ЎеӣһгҒ«з¶ҡгҒҸ