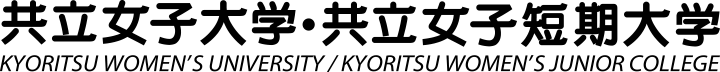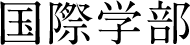Faculty of International Studies
еӣҪйҡӣеӯҰйғЁгғӢгғҘгғјгӮ№и©ізҙ°
жӣҙж–°ж—Ҙпјҡ2019е№ҙ12жңҲ26ж—Ҙ
з ”з©¶зҙ№д»Ӣ
гҖҗеӣҪйҡӣеӯҰйғЁгҖ‘гғӘгғ¬гғјгғ»гӮЁгғғгӮ»гӮӨ2019 пјҲ20пјүж©Ӣе·қдҝҠжЁ№гҖҢж—Ҙжң¬гӮўгғӢгғЎгҒ®гғўгғ©гғ«гғҗгғғгӮҜгғңгғјгғігҖҖвҖ•й«ҳз•‘еӢІвҖ•гҖҚ
ж—Ҙжң¬гӮўгғӢгғЎгҒ®гғўгғ©гғ«гғҗгғғгӮҜгғңгғјгғігҖҖвҖ•й«ҳз•‘еӢІвҖ•
ж©Ӣе·қ дҝҠжЁ№
гҖҖгӮўгғӢгғЎгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ«гғўгғ©гғ«гғҗгғғгӮҜгғңгғјгғігҖҒеӣәгҒҸиЁігҒӣгҒ°йҒ“зҫ©зҡ„ж”ҜжҹұгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒҢеҝ…иҰҒгҒӢгҒЁиЁҖгҒҲгҒ°гҖҒгҒқгҒҶгҒ гҒЁзӯ”гҒҲгӮӢгҒ®гҒҜйӣЈгҒ—гҒ„гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮе®ҹйЁ“зҡ„гғ»иҠёиЎ“зҡ„гҒӘдҪңе“ҒгҒҜгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®гӮўгғӢгғЎдҪңе“ҒгҒҜгҒқгҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гӮ’ж„ҹгҒҳгҒҰдҪңгӮүгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ
гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеҝ…гҒҡжҳҺзўәгҒӘгғўгғ©гғ«пјҲеҖ«зҗҶиҰігғ»йҒ“еҫіж„ҸиӯҳпјүгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгӮўгғӢгғЎгғјгӮ·гғ§гғігӮ’еҲ¶дҪңгҒ—гҒҹгҒ®гҒҢгҖҒй«ҳз•‘еӢІпјҲ1935пҪһ2018пјүгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғӢгғЎзӣЈзқЈгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгҒқгҒ“гҒ«гҒҜгҖҒй«ҳз•‘еӢІгҒҢгғ•гғ©гғігӮ№гҒ®гӮўгғӢгғЎжҳ з”»гҖҺгӮ„гҒ¶гҒ«гӮүгҒҝгҒ®жҡҙеҗӣгҖҸпјҲзӣЈзқЈгғқгғјгғ«гғ»гӮ°гғӘгғўгғјгҖҒ1953е№ҙж—Ҙжң¬е…¬й–ӢпјүгҒ«еҲәжҝҖгҒ•гӮҢгҒҰгӮўгғӢгғЎгғјгӮ·гғ§гғігӮ’еҝ—гҒ—гҖҒжқұдә¬еӨ§еӯҰд»Ҹж–Ү科гҒӢгӮүжқұжҳ еӢ•з”»гҒ«е…ҘзӨҫгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶиғҢжҷҜгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҖҺгӮ„гҒ¶гҒ«гӮүгҒҝгҒ®жҡҙеҗӣгҖҸгҒҜгҒ®гҒЎгҒ«ж”№дҪңгҒ•гӮҢгҖҺзҺӢгҒЁйіҘгҖҸгҒЁгҒ—гҒҰ1980е№ҙгҒ«е…¬й–ӢгҒ•гӮҢгӮӢгҒҢгҖҒй«ҳз•‘гҒҜе…ғгҒ®гҖҺгӮ„гҒ¶гҒ«гӮүгҒҝгҒ®жҡҙеҗӣгҖҸгҒёгҒ®ж„ҹйҠҳгӮ’дёҖеҶҠгҒ®жң¬пјҲгҖҺжј«з”»жҳ з”»пјҲгӮўгғӢгғЎгғјгӮ·гғ§гғіпјүгҒ®еҝ—вҖ•гҖҢгӮ„гҒ¶гҒ«гӮүгҒҝгҒ®жҡҙеҗӣгҖҚгҒЁгҖҢзҺӢгҒЁйіҘгҖҚгҖҸпјүгҒ«гҒ—гҒҰзҶұгҒҸиӘһгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖгҖҲгҖҺеӨӘйҷҪгҒ®зҺӢеӯҗгғӣгғ«гӮ№гҒ®еӨ§еҶ’йҷәгҖҸпјҲ1968е№ҙпјүгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдҪңе“ҒгӮ’гҒӨгҒҸгӮҚгҒҶгҒЁгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гҖҒгҖҺгӮ„гҒ¶гҒ«гӮүгҒҝгҒ®жҡҙеҗӣгҖҸгҒ®еӯҳеңЁгҒ«еҠұгҒҫгҒ•гӮҢгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҒ—гҖҒгҒқгҒ“гҒ«зӨҫдјҡж§ӢйҖ гӮ’жҢҒгҒЎиҫјгӮ“гҒ гӮҠгҖҒеҫ®еҰҷгҒӘеҝғзҗҶжҸҸеҶҷгҒ«жҢ‘жҲҰгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒгҒӨгҒҹгҒӘгҒ„гҒӘгҒҢгӮүйҡ е–©гӮ„иұЎеҫҙгӮ’ж•ЈгӮҠгҒ°гӮҒгҒҹгҒ®гӮӮгҒқгҒ®еҪұйҹҝгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҖү
гҖҖгӮўгғӢгғЎгҒ«зӨҫдјҡж§ӢйҖ гӮ„еҝғзҗҶжҸҸеҶҷгӮ’жҢҒгҒЎиҫјгӮҖж„Ҹж¬ІгҒҜгҖҒй«ҳз•‘еӢІгҒҢдё»дҪ“гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰдҪңгҒЈгҒҹдҪңе“ҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҖҺгғӣгғ«гӮ№гҖҸгҒ®иҲҲиЎҢзҡ„еӨұж•—гҒ«гӮҲгӮҠжқұжҳ еӢ•з”»гӮ’еҺ»гҒЈгҒҹгҒӮгҒЁгҖҒпјЎгғ—гғӯгғҖгӮҜгӮ·гғ§гғігӮ’зөҢгҒҰж—Ҙжң¬гӮўгғӢгғЎгғјгӮ·гғ§гғігҒ«з§»гҒЈгҒҰдҪңгҒЈгҒҹгҖҺгӮўгғ«гғ—гӮ№гҒ®е°‘еҘігғҸгӮӨгӮёгҖҸпјҲ1975е№ҙпјүгғ»гҖҺжҜҚгӮ’гҒҹгҒҡгҒӯгҒҰдёүеҚғйҮҢгҖҸпјҲ1976е№ҙпјүгғ»гҖҺиөӨжҜӣгҒ®гӮўгғігҖҸпјҲ1979е№ҙпјүгҖҒгҒқгӮҢгҒ«гҖҺгҒҳгӮғгӮҠгғіеӯҗгғҒгӮЁгҖҸпјҲ1981е№ҙпјүгғ»гҖҺгӮ»гғӯејҫгҒҚгҒ®гӮҙгғјгӮ·гғҘгҖҸпјҲ1982е№ҙпјүгҖҒгӮёгғ–гғӘдҪңе“ҒгҖҺзҒ«еһӮгӮӢгҒ®еў“гҖҸпјҲ1988е№ҙпјүгғ»гҖҺгҒҠгӮӮгҒІгҒ§гҒҪгӮҚгҒҪгӮҚгҖҸпјҲ1991е№ҙпјүгғ»гҖҺе№іжҲҗзӢёеҗҲжҲҰгҒҪгӮ“гҒҪгҒ“гҖҸпјҲ1994е№ҙпјүгғ»гҖҺгғӣгғјгғӣгӮұгӮӯгғ§гҖҖгҒЁгҒӘгӮҠгҒ®еұұз”°гҒҸгӮ“гҖҸпјҲ1999е№ҙпјүгғ»гҖҺгҒӢгҒҗгӮ„姫гҒ®зү©иӘһгҖҸпјҲ2013е№ҙпјүгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҖҒзӨҫдјҡзҡ„иҰ–зӮ№гҒЁдәәй–“еҝғзҗҶгҒ®жҙһеҜҹгӮ’ж¬ гҒ„гҒҹдҪңе“ҒгҒҜз„ЎгҒ„гҖӮ
гҖҖй«ҳз•‘еӢІгҒҢгҖҺгӮ„гҒ¶гҒ«гӮүгҒҝгҒ®жҡҙеҗӣгҖҸгҒӢгӮүеҸ—гҒ‘гҒЁгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒҜеӨҡж§ҳгҒӘгӮӮгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҒ гӮҚгҒҶгҒҢгҖҒеҶ·й…·гғ»йқһжғ…гҒӘгҖҢжҡҙеҗӣгҖҚгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢзҫ©жҶӨгҒЁжҠөжҠ—гҒ®зІҫзҘһгҒёгҒ®е…ұж„ҹгҒҢжңҖгӮӮеӨ§гҒҚгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҖҒз§ҒгҒҜиҖғгҒҲгӮӢгҖӮгҒқгҒ®ж„ҹиҰҡгҒҢгӮҲгҒҸзҸҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгҖҺгғӣгғ«гӮ№гҖҸгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҖҺзҒ«еһӮгӮӢгҒ®еў“гҖҸгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ
гҖҖгҖҺеӨӘйҷҪгҒ®зҺӢеӯҗгғӣгғ«гӮ№гҒ®еӨ§еҶ’йҷәгҖҸгҒҜгҖҒе…Ҳиј©гӮўгғӢгғЎгғјгӮҝгғјеӨ§еЎҡеә·з”ҹгҒ®жҺЁи–ҰгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҲқгӮҒгҒҰй•·з·ЁгӮўгғӢгғЎжҳ з”»гҒ®жј”еҮәгӮ’д»»гҒ•гӮҢгҒҹгҖҒй«ҳз•‘еӢІгҒ®гғҮгғ“гғҘгғјдҪңгҒ«гҒ—гҒҰгҒқгҒ®зңҹдҫЎгҒҢйҒәжҶҫгҒӘгҒҸзҷәжҸ®гҒ•гӮҢгҒҹдҪңе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ®гҒЎгҒ«гӮ№гӮҝгӮёгӮӘгӮёгғ–гғӘгҒ®зөҢе–¶иҖ…гҒЁгҒӘгӮӢйҲҙжңЁж•ҸеӨ«гҒҜеҫій–“жӣёеә—гҒ®з·ЁйӣҶиҖ…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒйӣ‘иӘҢгҖҺгӮўгғӢгғЎгғјгӮёгғҘгҖҸгҒ®еүөеҲҠпјҲ1978е№ҙпјүгӮ’д»»гҒ•гӮҢгҖҒгӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғјгӮ’еҸ–гӮҠгҒ«иЎҢгҒЈгҒҹй«ҳз•‘еӢІгғ»е®®еҙҺй§ҝгӮігғігғ“гҒ®еј·зғҲгҒӘеҖӢжҖ§гҒ«йӯ…гҒӣгӮүгӮҢгҒҹгҖӮгҒҷгҒҗгҒ«гҒҹгҒҫгҒҹгҒҫеҗҚз”»еә§гҒ§дёҠжҳ гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖҺгғӣгғ«гӮ№гҖҸгӮ’иҰӢгҒҰгҖҒгҒқгҒ®зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ•гҒ«ең§еҖ’гҒ•гӮҢгҖҒд»ҘеҫҢгҒөгҒҹгӮҠгҒ®гӮўгғӢгғЎдҪң家гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«е°ҪеҠӣгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
гҖҖгғӣгғ«гӮ№гҒҜжӮӘйӯ”гӮ°гғ«гғігғҜгғ«гғүгӮ’жқ‘дәәгҒҹгҒЎгҒЁеҠӣгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҖҢеӨӘйҷҪгҒ®еүЈгҖҚгҒ§иЁҺгҒЎжһңгҒҹгҒҷе°‘е№ҙгғ’гғјгғӯгғјгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒжӮӘйӯ”еҒҙгҒ®гӮ№гғ‘гӮӨгҒ®еҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒҶгғ’гғӯгӮӨгғігҒ®е°‘еҘігғ’гғ«гғҖгҒ®ж–№гҒҢгҒ“гҒ®дҪңе“ҒгҒ®иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ’гғ«гғҖгҒҜжӮӘйӯ”гҒ®еҝғгҒЁдәәй–“гҒ®еҝғгҒ®й–“гҒ§жҸәгӮҢеӢ•гҒҚгҖҒжңҖеҫҢгҒҜгҒқгҒ®иә«гӮ’зҠ зүІгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҢдәәй–“гҖҚгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮжқ‘дәәгҒҹгҒЎгҒЁжү“гҒЎи§ЈгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„еӯӨзӢ¬гҒӘеҝғгҒ®жҢҒгҒЎдё»гҒ§гҒӮгӮӢгғ’гғ«гғҖгҒҜгҖҒгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§иҮӘеҲҶгҒ®еҫ“еғ•гҒЁгҒ—гҒҰеҚ‘еҠЈгҒӘзӯ–и¬ҖгӮ’е®ҹиЎҢгҒ•гҒӣгӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢеҶ·й…·гҒӘжӮӘйӯ”гҒЁгҖҒгҒЁгӮӮгҒҷгӮҢгҒ°иҮӘеҲҶгҒ®ж¬ІжңӣгҒ®е……и¶ігӮ„иҮӘе·ұдҝқиә«гҒ«иө°гӮҠгӮ„гҒҷгҒ„дәәй–“гҒҹгҒЎгҒ®дёӯгҒ§иӢҰжӮ©гҒ—гҖҒи‘ӣи—ӨгҒҷгӮӢгҖӮгҒ©гҒЎгӮүгӮӮиҮӘе·ұдёӯеҝғзҡ„гҒ§еҲ©е·ұеҝғгҒҢеј·гҒ„гҖӮгҒқгӮ“гҒӘдёӯгҒ§гғӣгғ«гӮ№гҒЁдёҖйғЁгҒ®дәәй–“гҒ гҒ‘гҒҢгҖҢгҒҝгӮ“гҒӘгҖҚгҒ®е№ёгҒӣгӮ’йЎҳгҒЈгҒҰиЎҢеӢ•гҒ—гҖҒжҲҰгҒҶгҖӮгҒқгҒ®гҖҢгҒҝгӮ“гҒӘгҖҚгҒ®дёӯгҒ«гғ’гғ«гғҖгӮӮе…ҘгӮҢгҒҰгҒҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖгғ’гғ«гғҖгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҖҒеҝғгҒ«й—ҮгӮ’жҠұгҒҲгҒҹиҝ·гҒҲгӮӢеӯҳеңЁгӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮӢзІҫзҘһгҒҢгҖҒжң¬еҪ“гҒ®гғўгғ©гғ«гғ»йҒ“еҫіеҝғгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮд»–дәәгҒ«е„ӘгҒ—гҒҸгҖҒе№ізӯүгҒ«гҖҒжӯЈзҫ©гҒ®еҝғгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰжҺҘгҒҷгӮӢж…ӢеәҰгҒ“гҒқгҖҢгғўгғ©гғ«гҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖй»’жҫӨжҳҺгӮӮзө¶иіӣгҒ—гҒҹгҖҒй«ҳз•‘еӢІгҒ®д»ЈиЎЁзҡ„еӮ‘дҪңгҖҺзҒ«еһӮгӮӢгҒ®еў“гҖҸгҒ«гӮӮгҒ“гҒ®зІҫзҘһгҖҒгғўгғ©гғ«гғҗгғғгӮҜгғңгғјгғігҒҢеҰӮе®ҹгҒ«иЎЁгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒгғҚгӮ¬гғҶгӮЈгғ–гҒӘеҪўгӮ’жҺЎгҒЈгҒҰгҖӮ
гҖҖгҖҢгҖҺзҒ«еһӮгӮӢгҒ®еў“гҖҸзӣЈзқЈгҒҷгӮӢгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж–Үз« гҒ§гҖҒй«ҳз•‘еӢІгҒҜдё»дәәе…¬гҒ®дёӯеӯҰз”ҹгғ»жё…еӨӘгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҲеҺігҒ—гҒ„иҰӘгҒ®еҠҙеғҚгӮ’жүӢдјқгӮҸгҒ•гӮҢгҒҹгӮҠгҖҒжӯҜгӮ’е–°гҒ„гҒ—гҒ°гҒЈгҒҰеұҲиҫұгҒ«иҖҗгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘзөҢйЁ“гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮеҚ‘еұҲгҒӘж…ӢеәҰгӮ’гҒЁгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӘгҒҸгҖҒжҲҰжҷӮдёӢгҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҖҒгҒ®гӮ“гҒігӮҠгҒЁгҒҸгӮүгҒ—гҒҰжқҘгҒҹйғЁйЎһгҒ«е…ҘгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҖпјҲдёӯз•ҘпјүгҖҖжё…еӨӘгҒҜжңӘдәЎдәәгҒ®гҒ„гӮ„гҒҢгӮүгҒӣгӮ„гҒ„гӮ„гҒҝгҒ«иҖҗгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгҒӘгҒ„гҖӮеҰ№гҒЁиҮӘеҲҶгҒ®иә«гӮ’гҒҫгӮӮгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«жҲ‘ж…ўгҒ—гҖҒгғ’гӮ№гғҶгғӘгӮЈгҒ®жңӘдәЎдәәгҒ®еүҚгҒ«иҶқгӮ’еұҲгҒ—гҖҒиЁұгҒ—гӮ’д№һгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮгҖү
гҖҖзҗҶдёҚе°ҪгҒ§еҶ·й…·гҒӘеӯҳеңЁгӮ’еүҚгҒ«гҖҒгғӣгғ«гӮ№гҒӘгӮүгҒ°гҖҢеӨӘйҷҪгҒ®еүЈгҖҚгӮ’гҒөгӮӢгҒЈгҒҰгҖҢгҒҝгӮ“гҒӘгҖҚгҒЁжҲҰгҒҲгҒ°иүҜгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеұ…еҖҷгҒ®иә«гҒ®жё…еӨӘгҒҜгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒе№јгҒ„еҰ№гҒ®зҜҖеӯҗгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒжӯҜгӮ’е–°гҒ„гҒ—гҒ°гҒЈгҒҰеұҲиҫұгҒ«иҖҗгҒҲгҖҒгғ’гӮ№гғҶгғӘгғјгҒ®жңӘдәЎдәәгҒ®еүҚгҒ«иҶқгӮ’еұҲгҒ—гҖҒиЁұгҒ—гӮ’д№һгҒҶеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҢгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮеҮәжқҘгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮйЈҹзі§йӣЈгҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гҖҒе№јгҒ„еҰ№гҒЁгҒөгҒҹгӮҠгҒ гҒ‘гҒ§жҡ®гӮүгҒҷйҒ“гӮ’йҒёжҠһгҒ—гҖҒгҒқгҒ—гҒҰж–Үеӯ—йҖҡгӮҠиҮӘж»…гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ
гҖҖгҒ‘гӮҢгҒ©гӮӮй«ҳз•‘еӢІгҒҜгҖҒгҒқгӮ“гҒӘжё…еӨӘгӮ’иІ¬гӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҖҢиҮӘеҲҶгҒ«е®Ңе…ЁгҒӘеұҲжңҚгҒЁеҫЎж©ҹе«ҢгҒЁгӮҠгӮ’иҰҒжұӮгҒҷгӮӢгҖҒгҒ“гҒ®жіҘжІјгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдәәй–“й–ўдҝӮгҖҚгӮ’жӢ’еҗҰгҒ—гҖҒжЁӘз©ҙгҒ®йҳІз©әеЈ•гҒ§жҡ®гӮүгҒҷгҒ“гҒ®е…„еҰ№гҒ«гҖҒзҫҺгҒ—гҒ„гғӣгӮҝгғ«гҒ®еӨўгӮ’еһЈй–“иҰӢгҒӣгӮӢгҖӮжЁӘз©ҙгҒ«жҡ®гӮүгҒҷе…„еҰ№гҒ®гҒ“гҒЁгӮ’е‘ЁиҫәгҒ®дәәгҒҹгҒЎгҒҜзҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒҢгӮүгҖҒж•‘гҒ„гҒ®жүӢгӮ’еҮәгҒ•гҒӘгҒ„гҖӮеҝғгҒҢеҶ·гҒҹгҒ„гҒ®гҒӢгҖҒжүӢгӮ’гҒ•гҒ—гҒ®гҒ№гӮӢдҪҷиЈ•гҒҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒ«гҒ—гӮҚд»–дәәгҒ®гҒ“гҒЁгӮҲгӮҠиҮӘеҲҶгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§жёҲгҒҫгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®еҶ·й…·гҒ•гҒҜгҖҒжҲҰдәүгҒ®гҒӣгҒ„гҒӘгҒ®гҒӢгҖҒдәәй–“гҒ®жң¬жҖ§гҒӘгҒ®гҒӢгҖӮ
гҖҖй«ҳз•‘еӢІгҒҜгҖҒзҸҫд»ЈгҒ«з”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҖҢгҒ©гӮҢгҒ гҒ‘гҒ®е°‘е№ҙгҒҢгҖҒдәәгҖ…гҒҢгҖҒжё…еӨӘгҒ»гҒ©гҒ«еҰ№гӮ’йӨҠгҒ„гҒӨгҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖҚгҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҖҒжё…еӨӘгӮ’еҝғгҒӢгӮүжҶҗгӮҢгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖжё…еӨӘгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҖҒзңҹгҒ«жҶҗгӮҢгӮҖгҒ№гҒҚеӯҳеңЁгӮ’жҺ¬гҒ„гҒӮгҒ’гҖҒгӮўгғӢгғЎгғјгӮ·гғ§гғігҒ«гҒ—гҒҰгҖҒиҰігӮӢдәәгҖ…гҒ®еҝғгҒ«еҲ»гҒҝгҒӨгҒ‘гӮӢгҖӮй«ҳз•‘еӢІгҒ®гғўгғ©гғ«гғҗгғғгӮҜгғңгғјгғігҒЁгҒҜгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ