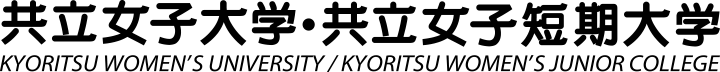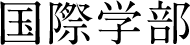Faculty of International Studies
国際学部取り組み・プロジェクト紹介 詳細
更新日:2017年05月08日
【国際学部】リレー・エッセイ(3) 西山暁義 「ドイツにおけるタトゥーの過去と現在」
ドイツにおけるタトゥーの過去と現在
西山暁義
2013年4月、私は在外研究を認められ、1年間ドイツ、ベルリンで暮らすことになった。その際、大学や公文書館などでの研究とともに、せっかくの機会ということで、壁の崩壊から約四半世紀が経つベルリンの街とその周辺を地下鉄やバスを使って訪ねて回った。
ちょうど日本では、前年に大阪の市営バスの運転手の刺青をめぐる問題が世論を騒がせていたころであった。その記憶もあって、バスに乗車する際、私の視線はどうしても運転手の腕や首筋に吸い寄せられていった。なめるように自分をのぞき込む気味の悪いアジア人、と思われたかもしれない。ともあれ、私が見たところ、男女を問わず刺青をしている運転手は少なくなかったが、日本で言われている場合のように、それが「乗客に不快の念を与えている」ようには見えなかった。
ドイツにおけるタトゥーの統計調査
実際、ドイツの代表的な世論調査機関である、アレンスバッハ研究所の2014年の調査によれば、ドイツ人の13%がタトゥーをしており、2003年から4%増加している。年齢別では、16~29歳の青年層ではその数は24%とほぼ倍増する。この数は、山本芳美『刺青と日本人』(平凡社新書、2016年)で挙げられているヨーロッパ全体の傾向や、フランスの場合ともほとんど変わりがない。さらに、アレンスバッハの調査によれば、ドイツ人全体では21%、青年層では46%が、タトゥーに対して好意的な印象を持っており、すでにタトゥーを入れた人の72%が、再び入れたいと考えているのだという。一方、ピアスはタトゥーに比べて人気がないようで、全体で7%、青年層でも15%にとどまる(ただし、ここでは「普通のイアリング」は対象外となっている)。
もちろん、こうした数は平均値であり、年代以外にどのような偏差が存在するのかも問題となる。すぐに思いつくのは性別であるが、(私にとっては)意外なことに、青年層の女性の方がタトゥー率は高く30%、それに対して同世代の男性は18%にとどまっている。他にも、統一前の東西ドイツに分けてみると、旧西ドイツ地域の青年層20%に対して、旧東ドイツ地域では41%と倍増する。さらに学歴については、日本での中学高校卒業にあたる基幹学校卒業者では33%、実科学校卒業者で29%、大学進学資格取得者の場合は14%と、学歴が高くなるにつれてタトゥー率は低くなる傾向にあるという。
ただし、タトゥーを低学歴、低所得に偏った現象と考えるには、大学進学者の7人に一人という数字は大きすぎるといえるだろう。ちょうど渡独直前の2013年初に行われたチェコの大統領選挙に立候補して話題となった、芸術家でプラハの演劇アカデミー教授でもあるウラディミール・フランツのように、顔全体を含め、身体の90%以上にタトゥーが施されているのは例外中の例外にしても、腕や首、背中などにポイント的に彫られたタトゥーをもつ者は、大学の私の研究者の友人のなかにもけっして多くはないが、複数存在した。また大学以外でも、10年ほど前に日本に遊びに来たルクセンブルク人の友人は、(よく語られるエピソードではあるが)一緒にスーパー銭湯に行って「刺青お断り」という掲示にショックを受けていたが、私は、クレディ・リヨネというフランスの有力銀行で働いていた彼がタトゥーを入れていたことをそこで初めて知り、むしろそちらの方に驚いた記憶がある。
歴史におけるタトゥー:「野蛮」と「魅惑」
歴史を振り返れば、ヨーロッパ人がタトゥーにエキゾチックな魅力を見出したことは、決して最近のことではない。「タトゥー」という言葉がポリネシア起源であることが示唆するように、とりわけ18世紀のジェームス・クックの探検航海は、ニュージーランドのマオリ族やポリネシア諸島の人々の身体の装飾文化に対する関心を高めることになった。もちろん、それは肯定的なものばかりであったわけではない。クックの5歳年上で、啓蒙時代のドイツの哲学者イマニュエル・カントは、マオリ族のタトゥーを身体の自然な美しさを歪めるものであると断じ、キリスト教を布教する宣教師たちも「異教時代への先祖返り」とみなしていた。その一世紀後には「犯罪人類学」の祖といわれるイタリア人チェーザレ・ロンブローゾが、工業化が進むヨーロッパ社会の文脈において、タトゥーは「文明化」されていない「精神的貧困」の象徴であると論じ、タトゥーをもつ労働者は潜在的な「犯罪者予備軍」を形成しているとみなされた。
しかし、こうしたタトゥーを「野蛮」、「反社会的」として忌避する考え方が広がる一方で、同じ時期、むしろ最も「文明化」されているはずの人々の間で、タトゥーに対する情熱が高まっていった。そしてそれには、「開国」した日本の「刺青文化」が大きく寄与していた。日本を訪れたヨーロッパの王族や軍人たちのなかには、彫り師にタトゥー(刺青というべきか)を彫らせたものが少なからずおり、その中には、のちの英国王ジョージ5世や、ロシア皇帝ニコライ2世、さらに第一次世界大戦のきっかけとなったサラエボ事件で斃れたオーストリア皇太子、フランツ・フェルディナンドらが含まれていた。付け加えれば、ハプスブルク家では他にも、皇后エリザベートがギリシャ旅行の際に美しい海の思い出として肩に錨のタトゥーを入れ、夫フランツ・ヨーゼフを仰天させたというエピソードもある(ブリギッテ・ハーマン『エリザベート―美しき皇妃の伝説』朝日文庫、2005年)。
ドイツについても、ジョージ5世やニコライ2世と従兄弟関係にある皇帝ヴィルヘルム2世の弟ハインリヒ(ニコライ2世とは「みいとこ(またいとこの子供同士)」の関係であるが、その妻アレクサンドラとジョージ5世とは、祖母がともにヴィクトリア女王である「いとこ」であった)が日本を訪れており、彼の刺青はその時入れたものである可能性が高い。兄の皇帝についてもタトゥーがあったという説もあるが、小山騰『日本の刺青と英国王室―明治期から第一次世界大戦まで』(藤原書店、2010年)も指摘するように、確実な証拠があるわけではない。ちなみに、同書は第一次世界大戦開戦時の参戦国の君主たちと同様、第二次世界大戦の連合国側の「ヤルタの三巨頭」―チャーチル、ルーズベルト、スターリン―もまた、皆タトゥー持ちであったことを述べて終わっている。ただし、(家紋のタトゥーを入れていたという)ルーズベルトについては、セオドアはほぼ定説のようであるが、フランクリンについては必ずしも断言できるわけではないようである。
第一次世界大戦前のドイツは、「遅れてきた植民地帝国」として、アフリカや南洋諸島に保護領を有していたが、そのなかには「タトゥーの故郷」サモアも含まれていた。ドイツの植民地統治は、現地先住民との混合婚を法的に禁止するなど隔離主義的側面が強調されるが、その一方で、最後のサモア総督であったエーリヒ・シュルツ=エーヴェルトは、malofie(あるいはPe’a)と呼ばれる、「勇敢な」男性として尊敬されるサモア人男性が身に付ける、腰から膝までの大掛かりなタトゥーを入れていた。たしかにヨーロッパの日常生活では露出しない部位ではあるが、それは完成まで数週間かかり、衛生面でも感染症のリスクが高く、見つかればスキャンダルとなってキャリアを失いかねない決断であった。統治する住民たちへの気軽なシンパシーの表明や、ましてや「サモア土産」としてできることではなかった(この点については最近刊行された、Matthew P. Fitzpatrick, “Embodying Empire. European Tattooing and German Colonial Power”, Past & Present 234(2017)、に詳しい)。
こうしたタトゥーを入れることは、サモアはあくまでドイツの支配下に置かれなければならない、という帝国主義と相反するものではなかった。しかし、たとえばウェイ・ダーチェン監督の『セデック・バレ』(2011年)で描かれた、台湾の原住民族に対する日本の植民地統治と比べてみるとどうであろうか。もちろん、サモアと台湾では民族や産業の構成も異なり、単純に比較することはできない。また、タトゥーを入れる部位の違いも関係しているかもしれない。しかし、明治維新後早くも1872年に「入れ墨禁止令」を出して職人や遊郭文化的な刺青をアウトロー化し、また「周縁」のアイヌや沖縄の刺青も撲滅の対象とし、さらにそれを植民地へと拡大していく日本の姿は、「文明国」として認められようとする強迫観念を象徴しているようにも見える。そして禁止令が戦後GHQによって廃止された後も、前出の山本芳美の本が詳述するように、今度は任侠映画などによって、「刺青=やくざ・暴力団」というイメージが作られていくことになる。
タトゥーのグローバル化
話を現在に戻せば、サッカー選手に芸能人、さらにはアカデミックな人間でもタトゥーをすることが決して珍奇なものではなくなっている現状は、ドイツでは”salonfähig”(社会的に許容されている)と形容される。しかし、それはタトゥーが当たり前のものとして無条件に受け入れられている、ということではない。2010年には、就任したヴルフ大統領(当時)の妻ベッティーナの二の腕のタトゥーをめぐって、「ファーストレディはタトゥーをしていてもよいのか」という議論が行われた(同時期にイギリスの首相となったデーヴィット・キャメロンの妻サマンサも、足首にイルカのタトゥーがあることが報じられていた)。また、極右の政治家がナチ賛美のタトゥーを公の場で露出したことで有罪判決を受けるといった、ドイツならではの問題もある。さらに、これはスイスの話であるが、最近、腕に大きなタトゥーを持つ若い女性司会者がラジオからテレビに転身し、ノースリーブで国会議員にインタビューをしている映像が流れたのに対し、テレビ評論家(高齢の男性)が「あり得ない」、「デコルテの方がずっとまし」と批判し、物議を醸している(記事の動画、写真を参照)。他にも(アメリカやニュージーランドの例であるが)、ミス・コンテストやキャビン・アテンダントにタトゥーを持った女性を認めるか、といったことも論争の対象となっている。現在の欧米が日本よりもタトゥーに寛容な社会であることは確かであろうが、そこでもこうしたせめぎあいがあり、それを通して、タトゥーが許容される社会空間はジワジワと広がっているということではないだろうか。
タトゥーはまた、アラブ世界においても広まりつつあるという。イスラム教の教義ではタトゥーは「ハラーム」として禁止されているものの、2014年末にはカイロではじめての「タトゥー見本市」が開かれ、厳格なスンニ派の国であるサウジアラビアでも、新聞がタトゥーの健康上の危険に注意を促すなど、大っぴらではないにしても、現実に若者たちの間で受け入れられるようになってきている。そしてそこには、「アラブの春」の挫折に対する幻滅の代償行為として鳥や翼などのタトゥーを入れる若者たちや、あるいはコーランの文言やパートナーの名前などを古典的なアラビア文字で刻みつけることで、イスラム教徒アラブ人としての伝統意識と、タトゥーという宗教的権威が否定する皮膚装飾を、束縛からの解放の象徴としてあえて結びつけるいう、興味深いアイデンティティの模索も見られる(レバノンの写真家バシャール・アラエッディーンのサイト”Arab ink”を参照)。おそらく、イスラム教徒の移民を多く受け入れているドイツやヨーロッパ諸国においては、タトゥーをめぐる選択の余地は、(葛藤を伴いつつも)より大きなものではないかと想像される(前述のアレンスバッハの統計には、「移民の背景」を持つか否かでの分類は残念ながらなかった)。
このように見ると、タトゥーはまさに文化のグローバル化の興味深い一例であると言える。そしてこのグローバル化は、けっして一方方向ではないし、欧米をたんに「タトゥー天国」などと考えるのも短絡的である。ますます多くの外国人観光客が来日するようになった現在、彼らに対する「おもてなし」の笑顔が引きつったものにならず、また(災害が起こった際に)偏見から思わぬトラブルが起きないようにするためにも、個人的にタトゥーを好むと好まざるとにかかわらず、それをめぐる「異文化」をより正確に理解する必要があるのではないだろうか。