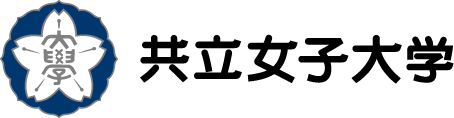
TOP > INTERVIEW 清水秀夫 教授
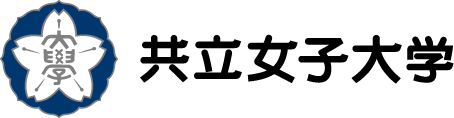
TOP > INTERVIEW 清水秀夫 教授
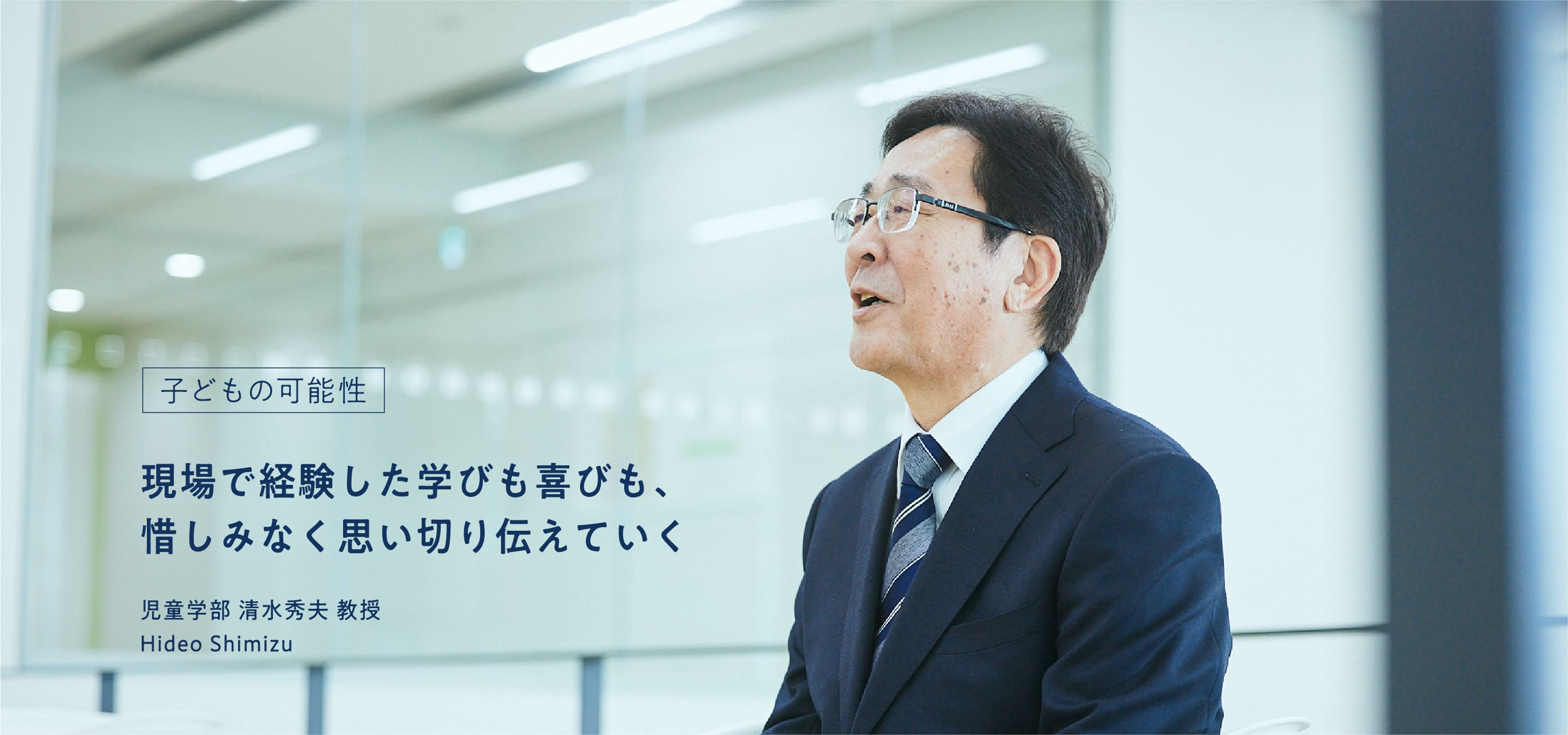
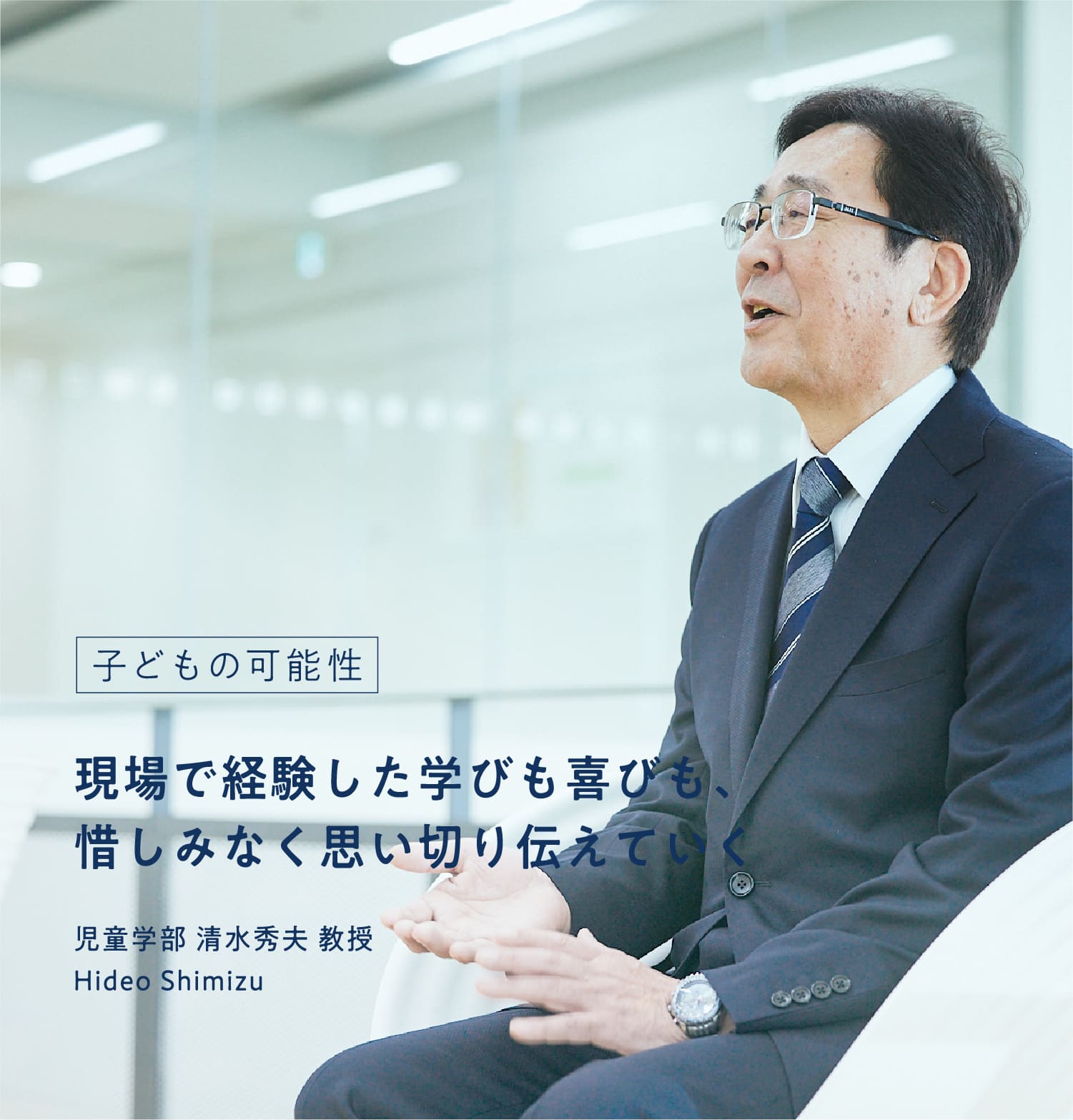

保育者・教育者の役割とは、子どもが願いを叶えるための援助だと思っています。そして、相手によって、シーンによって、どう手を差し伸べるかが、この仕事の難しいところです。子どもたちは一人ひとりに個性があり、毎日の成長も年齢や学年では決して測ることができません。ふさわしい支援や指導の仕方はそれぞれですから、子どもたちの可能性を広げるためには、教育の原理や心理、福祉、子育て支援など、児童学の幅広い知識や教養は欠かすことができません。
児童学部では、さまざまな専門分野をもつ教員から理論を学修し、フィールドワークや実習で理解を落とし込むことができるので、現場で生きる学びを身につけることができるのが特徴的です。小学校の実習先からは、「共立の学生は子ども一人ひとりをよく見ている」と言っていただくことが多いのですが、これは小学校教員を目指す場合も、幼児期について知識を深め、幼稚園での実習も経験するため。実践的に学んだ成果が、学生の行動の中にきちんと現れているのです。


私はかつて小学校の教壇に立っていました。児童学部には現場で活躍していた教員が多く在籍しています。教育現場はマニュアル通りにいかないことばかりですので、経験やエピソードも交えながらの講義も大切にしています。例えば、先生から保護者への電話連絡は時にネガティブな内容であることもありますが、たとえそうだったとしても、まず伝えるべきは子どもが頑張っている姿。できない子やヤンチャな子も、勉強ができる子やおとなしい子も、日頃から一人ひとりに目を向け、向き合っていれば、それぞれに良いところや成長があるものです。それを保護者にも伝えて信頼関係を築くことの大切さ、また、子どもたちを理解している存在が家族以外にもいるということが子どもたちの安心感に繋がり、彼らの今後の成長にも影響するということを学生のみなさんにも知ってほしいのです。日頃から私たち教員がまいている種は、学生の中でいつ芽を出すのかはわかりません。それでも、経験から学んだことも含めてできる限りのことを伝えていきたいと考えています。


学生は大きな夢を持って入学してきますが、1年次は将来のビジョンが漠然としていることもあります。しかし、2年次3年次と学びを重ねるに従って、将来なりたい姿は徐々に明確になり、悩みや相談ごとも具体的になってきます。また、実践力をつけるために模擬授業の数を増やして欲しい、実習までにこういうことをクリアしたいなど要望を伝えてくれる学生も出てきます。そういう変化にこそ、彼らの成長を感じて嬉しくなってしまうのです。
そして、私たち教員も学生の本気にも触発されて、教員同士で互いの授業を見あってよいところを授業に取り入れるなど、常に指導のレベルアップを目指しています。
子どもたちが成長していく姿を見ることができるのが、教員という仕事の最大の魅力。一人ひとりを見ていくのは大変なことですが、それこそが醍醐味でもあります。それは、小学校教員時代も、そして今現在も私自身が感じていること。教員という仕事の楽しさも喜びも、学生たちに存分に伝えていきたいですね。

