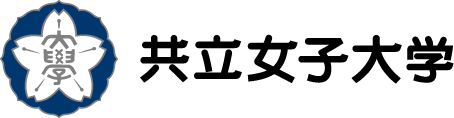
TOP > INTERVIEW 池上彰 客員教授
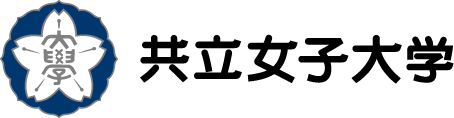
TOP > INTERVIEW 池上彰 客員教授

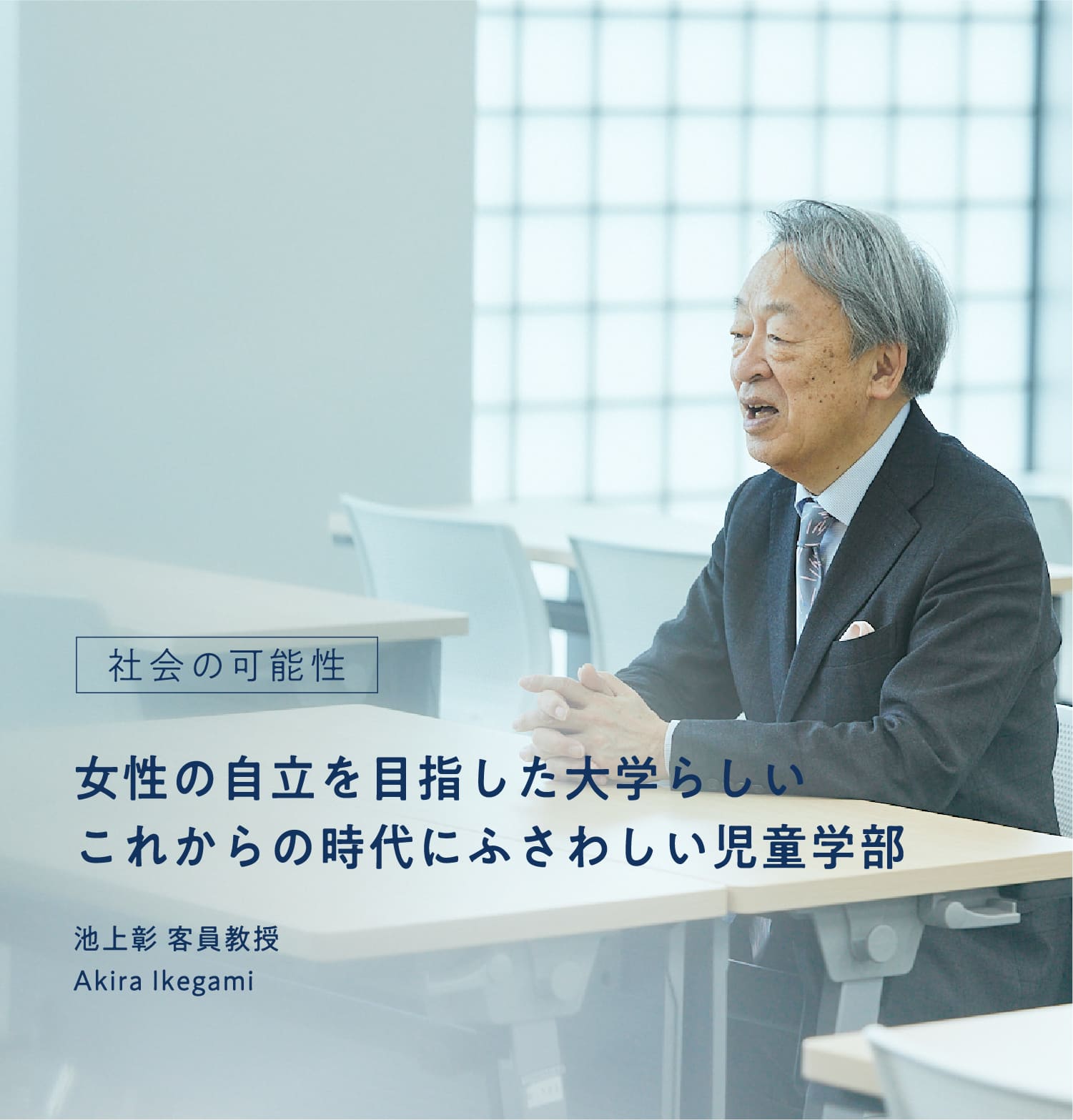

昨今深刻化している社会問題のひとつに「少子高齢化」が挙げられます。未来を担う子どもが少なくなっている今、彼らがいかにすくすくと人間的に成長できるかは、日本にも社会にとっても非常に大切なことです。
ところが、教育環境に目を向けると、教育者を目指す人は昔に比べると減少し、採用倍率が低下していることで質の高さを求めることは難しいとも言われます。そのような現状こそが、大きな社会問題ではないかと私は思っています。
保育所、幼稚園、小学校という幼少時期を過ごす環境は、勉強をするだけではなく人間形成の場。子どもたちは、人としての振る舞いや思いやりも、先生やクラスメイトとの交流の中で学び、豊かな心を育んでいきます。
「先生」という存在は、彼らにとって家族以外の最も身近な大人ですから、多大な影響を受けるのは言うまでもありません。人の成長に深く関わるものと考えると、教育者というのは極めて重要で尊い職業ではないでしょうか。


教育者になるための学部というと、子どもの知育についての研究や、勉強を教えるための術のようなイメージがあるかもしれません。そのような専門分野はもちろんですが、身につくスキルのひとつは、コミュニケーション力。小学校時代を思い返していただくと、先生が腰を落として子どもに話しかけている場面がありませんでしたか? それは膝をついてしゃがみ、子どもと目線を合わせるため。そして、そういう先生は、まず子どもの話を聞こうとしていたはずです。実は、対話で必要なのは、伝える力よりも聞く力です。優秀な先生が実践しているような対話術は、子どもだけでなく保護者に対しても有効ですし、どのような職種でも非常に役にたつ汎用性の高いスキルと言えるでしょう。
また、コミュニケーション以外も、児童学として学ぶ幅広い知識は、近年増えている子ども向けのサービスをはじめ、大人向けのサービスにも必要です。そして、児童学に基づくアイデアやスキルは、決してAIで置き換えられない価値の高いものなのです。
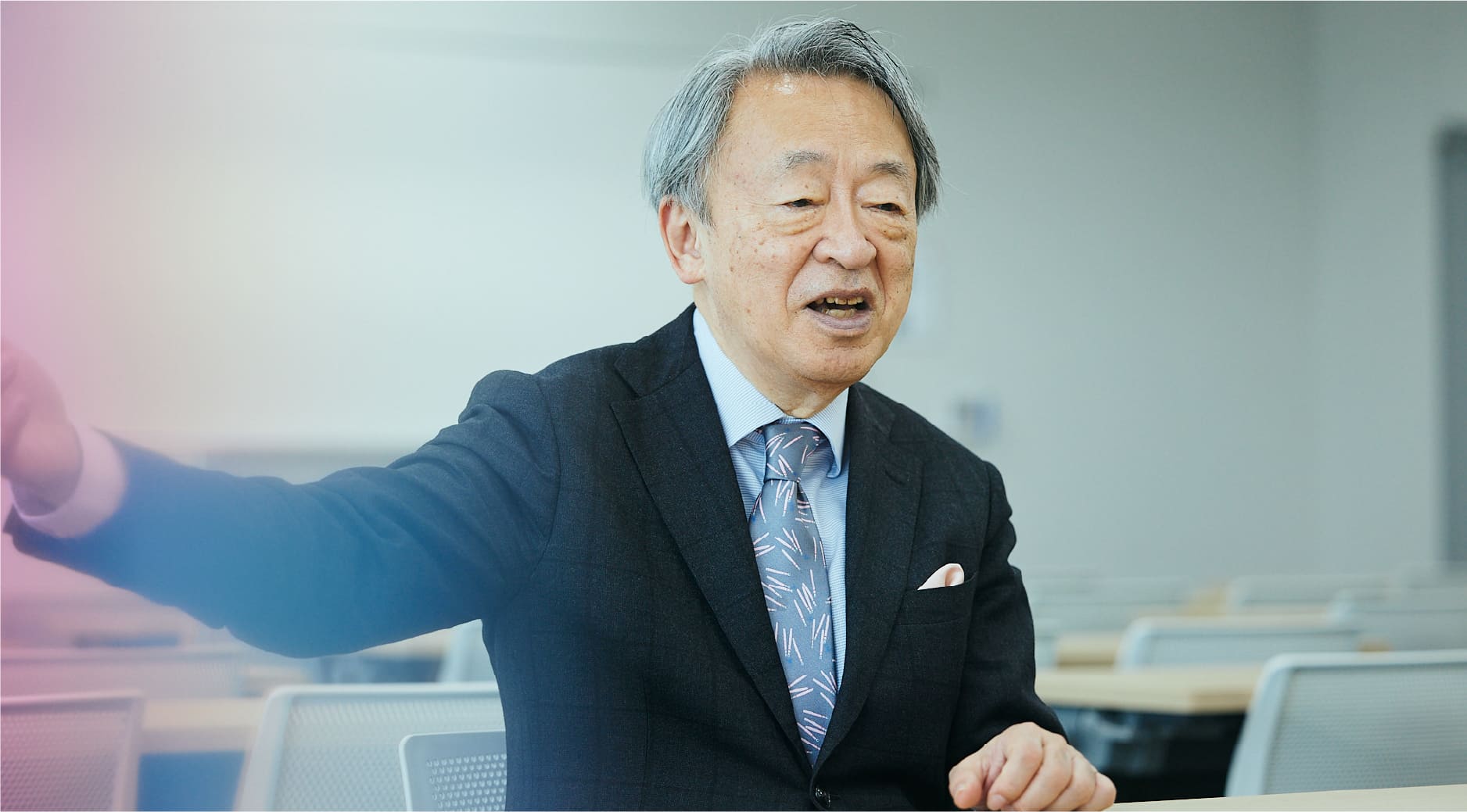

子どものことを学び接することは、人とはどういうものなのかを知るきっかけになりますし、彼らのお手本になれるだろうか、なるにはどうしたらいいだろうと模索する中で、自身を自覚したり育んだりします。そして、子どもと関わり社会に送り出すことが、社会の礎を築くことにも繋がっていきます。そう考えると、児童学は一石三鳥と言えるほど価値が高い分野。共立女子大学の児童学部の新設は、そのような意味で大きな可能性を感じずにはいられない嬉しいニュースでした。共立女子大学はもともと、良妻賢母を目指すことが当たり前だった時代に、女性も自立し活躍することに取り組んできた素晴らしい大学です。
私は、昔から変わらないその姿勢に共感して客員教授の依頼を受けました。ここで児童学を学ぶみなさんが、ひとりの人として、ひとりの女性として、自立した職業人として成長し、社会で活躍しながら日本の未来を明るく照らしていただけたら、と願っています。

