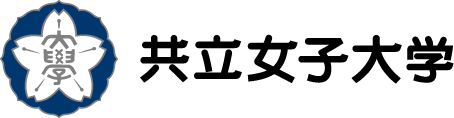
TOP > INTERVIEW 在学生
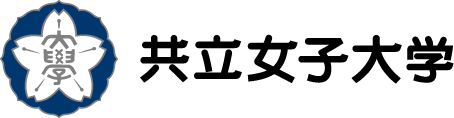
TOP > INTERVIEW 在学生



共立女子大学の児童学科での学びを振り返ると一番に思い浮かぶのは理論だけではなく実践力も身につくカリキュラム。手や体を動かしながら学ぶ内容も多く、自分自身が楽しみながら授業を受けることができたことです。私は子どもの頃から図工が得意ではなかったのですが、子どもたちにいかに楽しんでもらうかという観点が加わることによって取り組み方が変わり、工作への苦手意識も不思議となくなりました。子どもとの関わり方や向き合い方への学びを深める中で、1、2年次の「子どもと環境」「保育内容(環境)」の授業で学んだ廃品を使ったおもちゃづくりにも再び興味が湧き、幼稚園の先生になったらぜひ子どもたちと一緒にやってみたいと思っています。
また、現場で活躍していた先生方が多かったので、実際にあったことをベースにしたリアルなアドバイスをしてくださったり、先生が現場に立っていた様子を動画で見せていただけたりしたのは、とても参考になりました。


自分が大きく成長できたのは、保育・幼児教育学のゼミで学んだことだと思います。ゼミのメンバーと、ひとつのテーマについてデータを持ち寄って話し合ったり、興味深かった文献を共有してそれについて語り合ったり、先生や学生同士で密に意見を交わすことで、お互いを高めることができたと思います。また、卒業論文を書く際には、事例を収集するために公立の幼稚園に足を運び、子どもが遊んでいる時の表情や動き、先生の位置や声がけなどを細かく記録していきました。そして、自分なりにデータを分析し考察する過程の中で、より保育者の援助の重要性を知ることができました。
事例収集で訪れた幼稚園には、その後もボランティアとして行事ごとの準備を手伝わせていただきました。学生のうちからたくさんの現場経験ができたのはよかったですし、子どもと真っ直ぐに向き合い一緒に全力で遊ぶ先生の姿を見て、自分が将来なりたい姿を明確に思い描けたこともよかったと思っています。


大学で一緒に学んだ仲間は、「保育者」という同じ方向に向かっていたので、すぐに打ち解けることができ、勉強が大変な時もみんなに会えると思ったら前向きな気持ちで学校に行くことができました。就職を考える時期は、保育士か幼稚園教諭か、公立か私立か、または一般企業に勤めるのか、多岐にわたる選択肢の中で一人ひとりが迷いや悩みを抱えていましたが、共有しあって対話できたことで、それぞれが一歩を踏み出す決意ができました。
東京都特別区立の幼稚園を目指すことを決めてからは、同じ試験を受ける友達に声をかけ、励まし合いながら問題を解いたり予測問題を作って出し合ったり。友達が頑張っている姿にも鼓舞され、一緒に試験を乗り越えることができました。また、他学部と一緒に学ぶ教養教育科目の授業で看護学部の友達ができたのですが、彼女から聞く衛生管理の大切さや患者さんの気持ちの受け止め方の話は、保育にも通じるところがあり勉強になりました。4年間はあっという間でしたが、友達や恩師との出会いも成長できた日々も、一生の宝物だと思っています。

